|
|
|
�p�l���f�B�X�J�b�V����
���Z�b�V����
�u�V���ȒS����ɂ��܂��Â���̐��i�ƘA�g����������l����v |
|
|
|
|
|
�p�l���f�B�X�J�b�V����
���Z�b�V����
�u�V���ȒS����ɂ��܂��Â���̐��i�ƘA�g����������l����v |
|
|
�R�[�f�B�l�[�^�[�����H�Ƒ�w���݃V�X�e���H�w�ȋ����@�@�c�@���@�@�@���@�ǂ�����낵�����肢�������܂��B �@�܂��A�ǂ��������Ƃ��c�_�������̂��A�������\���グ�܂��B�g���h�Ɓg���h���������Ă͂����Ȃ��B�g���h�̕��ɒm�b�������āA���̒m�b����肭�g���āA���܂Łg���h���s���Ă�������T�[�r�X�A�Ⴆ�ΏZ���T�[�r�X�A�����T�[�r�X�A���̕������g���h��̂ŏ�肭���Ȃ��Ă����Ȃ��A�Ƃ����̂��b�肾�Ǝv���܂��B�g���h�����̕����ł��ƁA�����ȂǐF�X�ȖʂŁg���h�̏������K�v�ŁA�g���h�͎肮���˂������āA�{����Ȃ��ĉ�������̂�҂��Ă���͂��ł����A�g���h�̈ӌ����g���h�ɓ`����������Ȃ��B���ԑg�D�Ƃ������ƂŁA�^�E���}�l�[�W���[�̘b�����낢�날��܂����A�����̐l�ł����߂ł����A��w�l�ł����߂ł��B�g���h���{���ɂق������̂��A�g���h�ɂ�����Ɠ`������Ƃ��āA���E���ł��̒��ԑg�D���ǂ���邩�c�_���Ă���Ɨ������Ă��܂��B 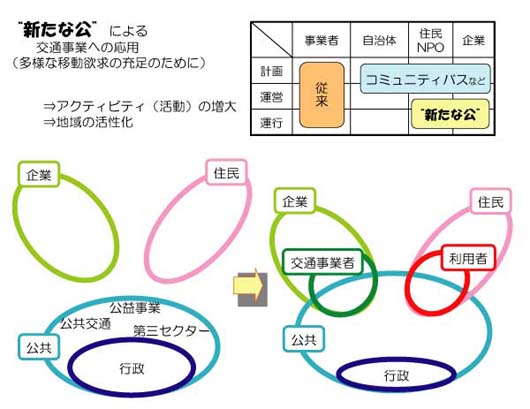 �@�F����̃��W�����̌��ɂ���̂ł����A�E�T�M�݂����Ȃ��̂��^�k�L�ɕς��b�ł��B�����̃E�T�M�Ɍ�����A��������Ă��镔�����̂ł��B�s���̕�������r�I�傫�������B��������͂ނ悤�Ɍ������������B��ƂƏZ���������B���ꂪ�A���q�����܂ߍ������������Ȃ�A�s�����ǂ�ǂ�@�\����߂Ă����B�������s���T�[�r�X�A�����T�[�r�X�A�Z���T�[�r�X�ł���A�g���h�Œ���̍s���T�[�r�X������낤�Ƃ������炢�̘b�ɂȂ��Ă��Ȃ����B�Ƃ��낪�A�����T�[�r�X�͏��q������܂߁A�L���ȎЉ�A���n�Љ�Ƃ������ƂŁA�j�[�Y���ǂ�ǂ�L�����Ă����B���̌����T�[�r�X�̕�����N���s���̂��B�s���͂ł��Ȃ��̂ł�����A���܂ł̊�Ƃ�Z���������T�[�r�X�ɓ��荞�݁A����`������Ƃ������Ƃł���܂��B�ł�����A�ꏏ�ɂȂ��Ă��̂ł͂Ȃ��A�g���h�̕������������Ă�邱�Ƃ��厖���Ǝv���܂��B �@����搶�̏��q����A�����Љ�A�n�����g���̂��b�ŁA�k�C���݂̂Ȃ炸�A���{�S�̂��k�ނ��Ă����B������ǂ�����Ċ��������Ă������B�����̎������コ����A�A�N�e�B�r�e�B���オ���Ă���Ƃ������Ƃł����A�V���Ȃ��Ƃ���̓I�Ɏn�߂�ۂ̖��_�́A�Z�����Ƃ������T�[�r�X��n�o�A�N�Ƃ��邱�Ƃł��B���̎��ɁA�ق��Ă�����g���h�̓{�����e�B�A�����Ȃǂ��킯���Ȃ��Ƃ����b�ł��B�N�Ƃ̌����́A��Ƃ͂����܂ł������A�Z���͘J���͂ł��B�ړI���Ȃ��A�����ŘJ���͂��o���Z�������邾�낤���B����͈��c�����܂Ƃ߂Ă����������b�ɋ߂��̂ł����A���͏Z���̋����A�V���p�V�[�A�܂��Â���̋����C���[�W�������Ă��Ȃ��ƁA�����n�܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B��Ƃ͊�Ƃł����������Ă��܂�����A���̂����������̎��v�g��̂��߁A�n��̐M��������̂��߂ɂb�r�q�Ƃ��ďo�����邾�낤�B�w��I�ɂ͂�����ł��`����b�ł��B�����܂ł͂��������F���������Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂����A�p�l���f�B�X�J�b�V�����̑O���́g���h�Ɓg���h�̊W�̋c�_�ł����A��i�͋�̓I�ȕ���Ƃ��āA�g���h�̊��Â���Ƃ��̉^�c�Ƃ��܂����B���̕ӂ���ނɂ��āA�c�_��i�߂Ă��������Ǝv���܂��B 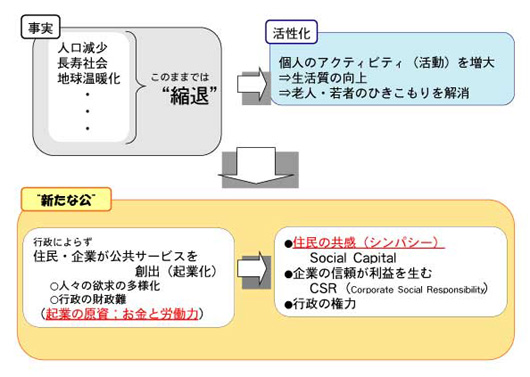 �@�ŏ��ɋc�_���Ē��������̂́A�g���h�Ɓg���h�̊W�͂ǂ�����ׂ����A�����̌o���܂��Ċe�l���炲�Љ���܂��B���̌�A�g�D�𗝉�������ŁA�܂��Â���̊������̂��߂ɁA�g���h�͉�������������A�g���h�͉�������������A��̓I�Șb�Ɍ��y�ł���Ǝv���܂��B �@���c����������A��낵�����肢���܂��B �p�l���X�g�D�y�w�@��w��w�@�����@�@���@�c�@���@���@��낵�����肢�������܂��B���茳�̃p���t���b�g�Ɏ��̌o���Ɗ�ʐ^���ڂ��Ă���܂��B���̎ʐ^���悭����ƁA�w�i�ɂ�����̎��肪�������G�Ȃ̂���������ɂȂ�Ǝv���܂��B���������������Ƃ����ƁA�{��玑�����̐����̗��G������M���m���悤�ɁA���͑�σA�o�E�g�Ȑ��i�Ȑl�Ԃ��Ƃ������Ƃł��B����Ȏ��ł����獡���̂��߂̃��W���������ɂ͂��p�ӂ��Ă��܂��A�p���[�|�C���g���̎������s���S�Ȃ��̂����������Ă���܂���B���̓_�͂��������������Ƃ����悸�͌�����ł��B �@�c������A���̌o�������班���b���ƌ����܂������A��{�I�ɂ͔��ɕn��Ȍo�������Ȃ��̂ŁA�I�m�ɂ������ł��邩�ǂ����s���ł����A�c�_�̒�N�ɂȂ�悤�ɏ��������I�Ȏ����������Ęb��i�߂Ă��������Ǝv���܂��B �@�`���ŁA�����̃e�[�}�ɂ��ēc�������蒸���܂������A���߂Ď��Ȃ�ɂ��̃Z�b�V�����̃e�[�}�����Ă݂܂����B�����̃e�[�}�͂R�̃T�u�e�[�}����\������Ă���̂��Ǝv���܂��B����́u�V���ȒS����v�A�u�܂��Â���v�A�u�A�g�v�̂R�ł��B �@�����͂��̕ӂɍS���āA���������ɃX�g�[���[��g�ݗ��ĂĘb��W�J���Ă݂����Ǝv���܂��B �悸�́u�V���ȒS����v�A�u�܂��Â���v�A�u�A�g�v�̃e�[�}��������Ă��鎖��Љ�����A�����ł����̎���̘_���I���Â��������͔w�i�ƂȂ��Ă���L�[���[�h����Ă��������Ǝv���܂��B�������ɍS������L�[���[�h�ɂ��ĂR�قNj��������Ǝv���Ă��܂��B �@����I�ɕ����Ă���Ɩ��C��͗l���܂��B���C�o�܂��ɏ�����������āA���茳�̃������ɂ����̃|�C���g���������߂Ă��������B �@��P�̘b��Ƃ��Ď���Љ��n�߂����Ǝv���܂��B�P�ڂ͓�������Ƃ��Ă̔��y���̃P�[�X�ł��B��グ���c�Z��̘b�ł��B���S�s�X�n�������̋�̓I�헪�Ƃ��āA�u�܂��Ȃ����Z�v�𑝂₵�Ă������߂ɂ͂ǂ����Ă����Ηǂ��̂��B�悸�ꕔ�̋c���������܂����B�c��ɂ����āA���S�s�X�n�Ɍ��c�Z��v��ː���8���鎖���c�����܂����B�m������܂ł͍x�O���ƒ��S���ł̔䗦���A�T�˂U�F�S����T�F�T���x���ł������v��ː����Q�F�W�ɕύX�����̂ł��B���̊�{���j�����ɗ��p���āA�ꕔ�̎��Ǝ҂��A���ƘA�g���Ȃ�����c�Z��̃o���G�[�V�����Ƃ��Ď�グ���Z�����݂��Ă������̂ł��B�n���s�s�Ƃ��Ă͌���I�ȏW�q�͎{�݂̈�ł���X�ǂ̈ړ]�v��ƘA�����镡���̏Z��v�������A�܂��̊�Â���ɐ����������Ⴞ�Ǝv���Ă��܂��B�����ɗ��Q�̈قȂ�4�҂����ꂼ��̗��Q�𗝉��������Ȃ���œK�l�̑g�ݍ��������s�����P�[�X�ł������Ƃ��đ����Ă��܂��B �@�����Q�ڂ̎���͊〈��s�̎���ł��B�〈��s�ł́A�s���̎��̌��ݎ��Ǝ҂̕������Ƌ�m�M�����^�C�A�b�v���u�o�e�h����v�𗧂��グ�A�V�������ƋƑԂ̉\����^���ɍl���Ă���܂��B�܂��A���̉��̂����߂��Ɂu�Ȃ��̂��ȁv�ƌĂ�Ă����̂̎s�ꂪ����܂������A�����̏ꏊ�Ƀ}���V���������ݒ��ł��B�����ł͎��Ԃ��]��ɂ�����܂���̂ŁA���ƊT�v�͏ڂ��������ł��Ȃ��̂ł����A�������Ƃ����̎d�g�݂��W�҂���\���Ƀq�A�����O����邱�Ƃ����E�߂��܂��B���̃v���W�F�N�g����͒n����Z�@�ւƒn�����ƎҁA�R�[�f�B�l�[�g�͂��������s���g�D�̎O�҂̋����W���ǂݎ���Ǝv���܂��B�X�ɂ͂��̃}���V�����̃}�[�P�b�g�̎�͑Ώہi�q�j�ł��鋳���̊w�������i�K����Q�悳�������Ƃ̌��ʂ������Ɍ�����Ǝv���܂��B�L�[�|�C���g�͉����E�E�E�܂��ɂ��̏ꍇ���u�g�ݍ��킹�A���Ȃ킿�A�g�Ƌ����v�ł��B �@�����ō�������ł��B�����炨�b�����钷�쌧�̏��z�{���ɍs���ꂽ���͂����܂����B�u�܂��Â���̒S����v�Ƃ����e�[�}�ɌW����i�I������������ꍇ�K���o�Ă��钬�ł��B���Ɏ������z�{���ɍS��̂́A�����g�����쌧�̏��{�̐��܂�ł��̂ŁA���z�{�͓����̋��ł��B����Ō̋��̐�`�����悤�ƁA�ǂ��֍s���Ă����z�{���̘b��\���グ�Ă��܂��B���́u�܂��Â���̒S����v�̍��O����Ƃ��Ă悭�o�ė���̂́A�X�y�C���̃o���Z���i�ł��B�o���Z���i�ł͓�����̂܂��Â���ɂ����āA�u�~�N���̓s�s�v��v���邢�́u����S�̂ցv�ƕ\������Ă���V�����d�g�ݏ����u�o���Z���i���f���v�ݏo���܂����B��قǍ���搶����A�x�R�s�̂k�q�s�̘b������܂����B���̂Ȃ��Ŏ��͓��Ɂu�^�s�̂��߂̃C���Z���e�B�u�Ƃ��Ă̐ŋ��Ə��v�Ƃ�����������ۂɎc���Ă��܂��B�k�q�s�Ɋւ��Ă̓t�����X�̃X�g���X�u�[���Ƃ����X�ł̓W�J���ł��L���ł��B�X�̃V���{���ł���k�q�s�������߂ɁA��ʓ��ʖ@�𐧒肵�ΘJ�҂���1.75���̌������s���k�q�s�̉^�s�Ԏ��ɏ[�����Ă��܂��B�k�q�s���X�̃V���{���Ƃ��Ĉʒu�Â��A�����������s�s����̊�Ƃ��邱�Ƃɂ��āA���̂悤�ɂ��Ďs���̍��ӌ`���������t���Ă��邵�������Ƃ�������s�s������_�Ԍ��鎖���o���܂��B �@�����܂łɔ��y���A�〈��s�A���z�{���A�o���Z���i�A�����č���搶�̘b�̉�����ŋ}篕t���������X�g���X�u�[���̎���ɂ��ċ}�����ŏЉ�Ă��܂����B �@�����܂��Ă����̎���̘_���I���Â��������͔w�i�ƂȂ��Ă���L�[���[�h�ɂ��Ăł��B����ɂ��Ă��F����̂��茳�ɂ́A������Ƃ����������p�ӂ���Ă��Ȃ��Đ\����܂���B���Ȑ�`�ɂȂ�܂����A�����炨�b��������e�́u�k�m��s�������|�[�g�U�E�V�����v�ɁA��20�y�[�W�ɂ킽���ďڂ����f�ڂ���Ă���܂��B�k�m��s�̃z�[���y�[�W���炩���邢�͋�s�̑����Ō��������ł��܂��̂ŁA������ǂ������������Ǝv���܂��B �@�L�[���[�h�̂P�Ԗڂ́A�uNew �o�o�o�v�ł��B�o�o�o�Ƃ́Apublic�Aprivate�Apartnership�̓������ł��B�o�o�o���T���I�ɐ������܂��B�ێ�}�����̃T�b�`���[�̎���ɍs�����v�̒��Ƃ��Ăo�e�h�����i����܂������A���̉ߒ��ɂ����đ����̏�ʂɂ����ė\�����Ȃ��������o�ė��܂����B�����ło�e�h�̂����_���O���C�����Ȃ��炻�̑R���Ƃ��ĘJ���}�����̃u���A���ł��o�����o�o�o�ł��B��X�͊����Ă��̂o�o�o�̑O��New�Ƃ��܂����B���̂��Ƃɑ��đ����ȋc�_������܂������Ƃ������ł��B�����Ȃ���New�Ȃ̂��A�������Ղɂ��邱�Ƃ͔F�߂��Ȃ����Ƃ����c�_���A��X�̊Ԃł����Ȃ范��������܂������A�ӂɉ��New�o�o�o�Ǝ��͌��������Ă���܂��B �@�}�����Ă����������������̒ʂ�A���܂ł̎Љ�ʔO�Ƃ��čs���A�s���i�Z���j�A��Ƃ̎O�̃Z�N�^�[������܂����BNew �o�o�o�̈Ӑ}���鏊�̓X�L���A�b�v��K������������]���̂R�̃Z�N�^�[�ɁA�m�o�n�A�R�~���j�e�B�r�W�l�X�A�o�e�h�E�q�e�o�Ȃǂ̑g�D��`�Ԃ������U�ƂȂ����Z�N�^�[���A���ꂼ��ɃX�e�[�N�z���_�[�Ƃ��Ă̈ӎ��������A���ꂼ��̗��ꂩ�瑊�݂ɂ������I�ɘA�g��}���Ă������̂ł��B����́u�V���ȒS����v���Ƃ����܂��B�X�L���A�b�v���ꂽ�O�̃Z�N�^�[�Ƃ͈ȉ��̂悤�ȃC���[�W�ł��B�s���Z�N�^�[�ɂ����Ă͍s���ɑ����郌�x���̏Z���ł͂Ȃ��A�V�`�Y���V�b�v���������Z�����Ȃ킿�{���̎s���ɂȂ鎖���K�{�ł��B�܂��s���Z�N�^�[�ɂ����ẮA�s���}���͂m�o�l��ڕW���̈�Ƃ��āA�n��̌ڋq���������g�D�ƂȂ�ׂ��^���ȋC�����Ŋ������A�ߑ��𒅒����Ă��畑��ɏオ���Ă��Ă��������B��Ƃɂ����Ă͍������ɂȂ��Ă���R���v���C�A���X�Ȃǂ͋c�_�ȑO�̖��ł��B��قǏo�Ă����b�r�q�E��Ƃ̎Љ�I�ӔC�܂ł�����Ɗ�Ɠ��Ő������ēy�U�ɏオ���Ă��Ă��������Ƃ������Ƃł��B���ɒn��̊�Ƃɂ͊��҂��鎖���傫���B�Ȃ��Ȃ�Βn��������A�n����Đ����Ă������A�{�����e�B�A������W�҂̈ӎu�A�v�������ł͒n�悪�ς�邱�Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��邩��ł��B����I�ɂ����ɕK�v�Ȃ̂͊�Ɨ͂�o�c�͂̃Z���X�ł��B��ƈȊO�ł��s���̓R�~���j�e�B�r�W�l�X�͋N�����Ă����܂�����A�s���Z�N�^�[�ɂ����Ă�����Ƃ���Ɨ͂�o�c�͂̊��o��g�ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B 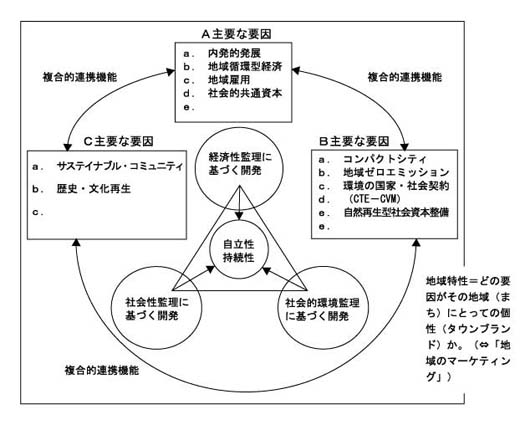 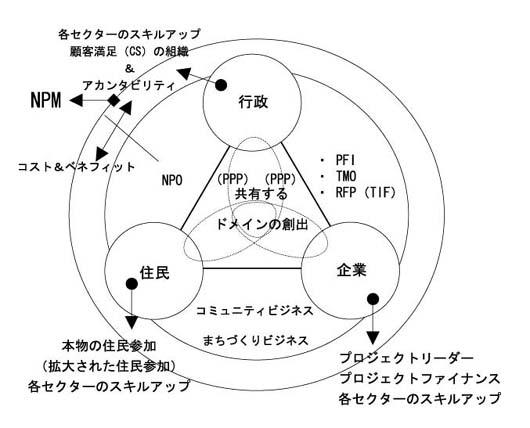 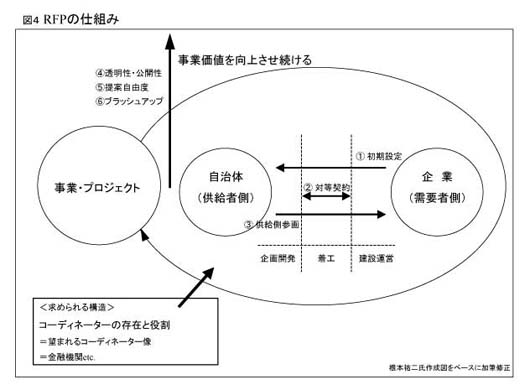 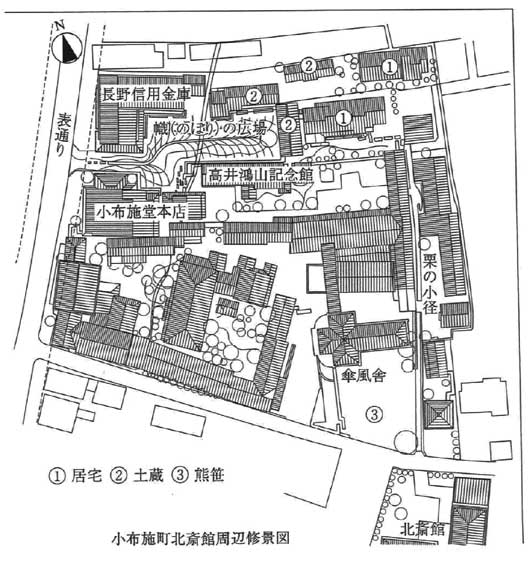 �@�Q�Ԗڂ̃L�[���[�h�͂q�e�o�ł��B�q�e�o�Ƃ�request for proposal�̓������ł��B��������Ԃ�����܂���ڂ����͐����ł��Ȃ��̂ł����A�v����Ɋ��Ɗ�Ƃ��Γ��ȗ���ŁA�����݂̗ǂ��Ƃ�����o�������Đ^����������v���W�F�N�g�`�Ԃł��B���̎��Ɉ�ԑ厖�Ȃ̂́A�R�[�f�B�l�[�^�[�̑��݂ł���A���̖����́A�n���Ƃ��S���ׂ����Ɠ��m��̍��{����͎咣���Ă��܂��B��قNJ〈��s�̎���̂Ȃ��ł��b�����Ƃ���A�o�e�h����̃R�[�f�B�l�[�^�[���Ƃ��ċ�m�M���̒����̕����^���Ɋւ���Ă��܂����B���̈Ӗ��ŁA�〈��s�͂��̂q�e�o�̎d�|���̃��f���P�[�X�ɂȂ��Ă�����\�����傾�Ǝv���Ă���܂��B �@�Ō�ɎO�Ԗڂ̃L�[���[�h�ł��B�F����̑O�Ɏ����Ă��܂��̂��A���z�{���̂܂��̍Đ��̐}�ʂł��B���̃G���A�͏��z�{���̂܂��Đ��̋N�_�ƂȂ����|�C���g�ł�����A�F��������̐}�ʂ͐F�X�ȏ��ň�x�͖ڂɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Łu�G���A�}�l�[�W�����g�v�Ƃ����O�ڂ̃L�[���[�h�����������Ǝv���܂��B�ēx�\���܂��ƁA�����̂R�̃L�[���[�h�Ƃ́A�@New�o�o�o�A�A�q�e�o�A�B�G���A�}�l�[�W�����g�ł����A���z�{���ɂ����邱���ł̓W�J�̓G���A�}�l�[�W�����g�̎��ɍD�Ⴞ�Ǝv���Ă��܂��B���z�{���Ƃ������َq���A��������A�M�p���ɁA���z�{���A�l�̖��ƂQ���������ł܂��̊��n��o�����u�n���s�s�ɂ�����G���A�}�l�[�W�����g�v�Ƃ��Ẵv���W�F�N�g�ł��B���茳�̊����}�����Ă��������B���̐}�ʂł����A���x���̕ӂɂ��������ƂQ�����A�������ꂽ���̃|�C���g�ɉg�Ƃňړ������A���̐Ւn�ɂ͐M�p���ɂ��V�z�ړ]���A�M�p���ɂ̓y�n���������A���̈ꕔ������ɔ���܂����B�p�n���������������́A�����̑��Ɨאڒn�Ɋ��ɂ��������z�{���̃f�U�C���ƒ��a�������X�ܓW�J��}��܂����B�c��̗p�n�͏��z�{�������c�̒��ԏ�E�C�x���g�L��ɂ��܂����B�ʓ˂����̐��������A�T�҂̒N�����������Ȃ��Ƃ����G���A�}�l�[�W�����g�ł��B �@�n���I�Ɍ��āA��s���R�O�O�O���l�Ƃ�����}�[�P�b�g�ɋ߂��Ƃ������������邱�Ƃ����������Ă��A�N��300���l�O��̊ό��q���K��Ă��錋�ʂ͑傫���]�������ׂ����̂��Ǝv���܂��B���̍ŏ��̐����ɐG������āA�܂��Â���̂��˂�͑傫�����S�̂ɍL�����Ă��܂��B�o���Z���i���f���̓ǂݑւ��ƌ����Ă悢�̂�������܂���B�S�̂��l����̂ł͂Ȃ��A����Ƃ����˔j����A�S�̂ɔg�y���Ă������낤�Ƃ����ǂ݂ł��B�����Ɍq����\���̍����G���A��I�����A�����Ő������f����������A�S�̂ɔg�y����B�S�̂̂��Ƃ��l����̂͂��܂�ɂ��ۑ肪�������邱�ƁA�����đS�Ẳۑ������}���Ă������߂ɂ͕K�v�ƂȂ邻�ꂾ���̂������G�l���M�[���Ȃ��̂������ł��A���ꂾ���炱������S�̂Ƃ����G���A�}�l�[�W�����g���K�v���Ǝv���܂��B�����̃e�[�}�u�V���ȒS����v�u�܂��Â���v�u�A�g�v�Ɋւ��鎖��Ƃ����̎���̘_���I���Â��������͔w�i�ƂȂ��Ă���L�[���[�h�ɂ��ďq�ׂ����đՂ��܂����B�����ł����ꂩ��̔M���c�_�̂��������ɂȂ�Ǝv���܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L���������܂��B���������āA��w�Ƃ܂��Â���̎���Ƃ��āA���삳��ɂ��肢���܂��B �p�l���X�g�k�C�������w���w���i�〈��Z�S���j�@�@���@��@���@�l�@�〈��Z�̍���ł��B���͕��w���Ƃ����E�ɏA���Ă��܂����A�����O�܂ł́A��w�̒��̒n��A�g�Ƃ����ψ���̈ψ����ł����B��Ɋ〈��Z�̏��������d�ˍ��킹��Ӗ��ŁA�〈��s�̒��ŁA�w���̒n��A�g�I�Ȋ������ł��Ȃ����Ɛi�߂ĎQ��܂����B�����͐F�X�Ȏ�������Љ�����Ǝv���܂����A���Ⴂ�ŁA���c�搶������ꂽ���Ƃ��S�R������܂���ł����B�ォ��A��������ɂ��ĕ��͂��Ē�����Ǝv���܂��B �@�܂��A�����w���Ȃ��A����̃e�[�}�ɂ���悤�Ȃ܂��Â���Ɋւ��̂��Ƃ������ƂŁA���w�̑g�D�̕ύX�ɂ��Ă��Љ�����Ǝv���܂��B����18�N����ς�����̂ł����A���̑O�́A�k�C���ɂ���T�L�����p�X���A���ꂼ�ꓯ���悤�Ȏd�g�݂Ŋw�������炵�Ă��܂����B�@�l�����}���A��w���Ǝ��Ōo�c����ɍ���������A���Ɋ〈��͋����{�����O���A�|�p�ƃX�|�[�c�ɓ��������V�����ے���͍����悤�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�{���ł��ƁA�����{����{�ō��܂ōs���Ă��܂����B�����w�Ƃ������̒ʂ�A�����{���𒆐S�ɍs���Ă����̂ŁA�ʂ����Ċ〈��ʼn����ł���̂��A�܂�������@�ł�����܂����B�����A���z��ς��܂��ƁA��@�͎��̃`�����X�ɂȂ��邱�Ƃ�����A��N����〈��̓����ł���|�p�ƃX�|�[�c�𒆐S�ɁA�����V�������Ƃ��ł��Ȃ����ƁA�n��A�g�W�ŐF�X�͍����ĎQ��܂����B���ɁA�|�p�ƃX�|�[�c�̂˂炢�ƂȂ���̂��o���܂����B�|�p�̂˂炢�́A�n��Љ�ɂ����ėl�X�ȕ����A�|�p�V�[�������o�ł���l�ނ̈琬�B����͑�w�̖ڕW�ɂ��Ȃ��Ă���܂��B�܂��A�X�|�[�c����ے��̂˂炢�́A�l�X�̌��N�ƁA�n��Љ�ɍv���ł���l�ނ̈琬�ł��B��̐��͂Ȃ��ł����A���ꂩ��̊〈��Z�̕�������������ł́A���Ɏa�V�Ȃ˂炢�ƂȂ�܂����B �@���̐V�����〈��Z���A�ǂ������������s���Ă����̂��B��N����ł��̂ŁA���܂葽���͂���܂��A���̒����炩���܂�ł��Љ�܂��B��Ɋ〈��s���ӂł̊����ł����A�܂��A���N�łR�N�ڂɂȂ�A�T�b�J�[����Ƃ��Ă���搶�̊����ł��B��ɒ��w���A�������łȂ��Ȃ�����ł��Ȃ��P�N����ΏۂɁA�����̒��w�Z����q���������W�߁A���ꂩ��w���҂ɂȂ蓾�鋳���w�����R�[�`�ɂ��A�N�T�炢�w�����C���s���܂����B�܂��A�V�����\�͂̊J���̂��߂ɁA���w���������Ďw�������Ă��܂��B�������̒n��ł̊����ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B �@���ꂩ��A�����T�A�U�N�̊����ɂȂ�܂����A������X�|�[�c�W�ł��B���w���̎q���������̒��Ŋ���������B����ɔ����āA�ċx�݂ɃL�����v�������s���Ă���܂��B���w�Z�̋��犈���̈�Ƃ������́A�w�Z�����ȊO�̎��R�Ȏ��Ԃ̒��ŁA�q�������ɐ쉺�A�J�k�[�A�L�����v�̊������s���Ă��܂��B�q�������ɂ͔��ɍD�]�ŁA���N�ċx�݂ɍs���Ă��܂��B �@��N12���ɍs�����̂́A�q���Ώۂł͂Ȃ��A����҂ő��������A���ꂩ�猒�N�𒆐S�ɍl���˂Ȃ�Ȃ��������ɁA�X�|�[�c�Ƃ������́A���N�̂��߂̉^�����H�����Ē������ƁA�ی��Z���^�[���ƘA�g���āA��w�̒��ʼn��\�h�ɓK�����^�������H���ĎQ��܂����B�〈��s���ւ̃X�|�[�c�I�Ȋւ��A�n��A�g�Ƃ��ĂR�_���Љ�܂����B �@���Ɍ|�p�ł����A���y�ʂł́A���܂ł��܂艹�y�I�Ȋ����̏Љ�Ȃ���Ă��Ȃ������̂ŁA�u���̐搶���s�������ɁA�u�܂Ȃ݁[��v���̉�����ăR���T�[�g���J���Ă��܂��B�����̉J���Ă���A�s���ł���Ζ����ŎQ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����������I�ȉ��y�Ƃ̃R���T�[�g�̑��ɁA�q�������ɁA���y���y�����̌����Ă��炤���݂��s���Ă��܂��B�Ⴆ�A�Ղ͓��{�×��̊y��ŁA����ɖ��b���d�ˍ��킹�A�q�������ɖ��b�ƌ×��̊y��Ƃ̃R���{���[�V�����ɂ��A�y�������������Ă��炨���Ƃ������̂ł��B���l�̊����̉����ɁA�u�������q�v�Ƃ����A�����Ȃ��q������������̂��ꂳ������W�܂�A���y��f�������p���Ȃ����炤�Ƃ��������s���Ă���܂��B��������Ȃ�D�]�ł���܂��B �@���p�n�ł́A�〈��s���̃r���ɁA���p�n�̊w�����G��`���Ă��܂��B�����̎s���̖ڂɐG��邱�ƂɂȂ�̂ŁA�������������ς�����Ƃ����]�����Ă��܂��B�U���Ɋ〈��w�ɂ��V�����Ȃ�܂������A���v���n�u�̉w�ɂ��P������邱�ƂɂȂ�A���̋��w�ɂŁA�����������W�܂��Ċ��ӂ���Ƃ������𗧂Ă܂����B����͊〈��s�ق��̃R���{���[�V�����ōs���܂������A���ɍD�]�ŁA�〈��s�̔��p�n�̊w�����傫�ȕlj��`�����ƁA���ɑ傫�ȕ]�����܂����B�ŋ߂ɂ́A���Ղ�̍ۂɈĎR�q�����܂����B��������������z���Ǝv���܂����A�w������������̂�X�̑O�ɓW������B�w�O�̏��X�X�ɂ͊��C���������X������̂ŁA�C�x���g�Ƃ��ĈĎR�q�������悵�܂����B�ŋ߂̓p���t���b�g���o�āA16�̓X�Ɋw������̈ĎR�q��W�����Ă���B�u�ĎR�q�Ƃ܂����킹�v�A�X�Ƒ҂������������ł���܂��B�w�O�𒆐S�Ƃ������X�X�̒��ɁA�w�����Ǝ��ɍ��グ���ĎR�q��W�����āA�s���̊F����ɑ����^��Œ������Ƃ��������s���Ă��܂��B �@�����钆�ŏ\�قǂ��Љ�܂����B���ꂪ�A��w�̋����A�w���ɂ�鎖�ƁE�����ł��B�����A���ꂪ�܂��Â���ɑ����ɂȂ���Ƃ͎v���Ă��܂���B��w�̂˂炢�ɂȂ�̂́A���I�Ȋw������Ȃ̂ŁA���̋�����s���ߒ��ŁA���̊������A�〈��s�܂��͋ߗׂ̂܂��Â���ɍv���ł���Δ��ɍK�����Ƃ����v���ŁA��N������g��ł���܂��B����̌o�߂ɂ��ẮA��قǂ������Ē����܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@����₢�����܂��B�w�������̏o�g�ł����A�{�B������������Ă��܂����B ����i�p�l���X�g�j �@�����͂Ȃ��ł����A�{�B��������Ă���܂��B�w���́g�悻�ҁh�ł��āA��قǂ̂��b�ɂ������̂́A�܂���ς���̂́u�悻�ҁA��ҁv�����āA���p�E���y�E�X�|�[�c�̔n���ł�����A���������Ӗ��ł͎O���q�������w�����〈��Ŋ������Ă���Ƃ������Ƃł��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�搶���͑S������ł��ˁB ����i�p�l���X�g�j �@�{�B�̑�w�ŕ����ꂽ�������Ă���܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L���������܂��B���͌�����ɂ��肢���܂��B �p�l���X�g�i�Ёj�k�C���J���Z�p�Z���^�|�����@�@���@�@���@�G�@���͌�ʂɊW���āA�ό��A�n��Â���A���̑��̃v���W�F�N�g���s���Ă��܂����A�����̃e�[�}�ɕ����āA���̎�����Љ�����܂��B �@��́A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���A������͌�����ʂŁA���ʂōs�����o�X�̍ĕ҂ł��B �@�܂��A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���ł����A���͗L���ӔC���Ԗ@�l�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�x���Z���^�[�̗���ƁA�Вc�@�l�k�C���J���Z�p�Z���^�[�̓�̗���ŁA�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���ɂ��ĕ������܂��B �@�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���ɂ́A�F�X�ȉ��߂�����܂����A��X�̓���I�Ȑ����Ƃ��āA�g�݂��h�����������Ƃ��āA�n��̕��X������ƂȂ�A�s�����ƂƘA�g���Ȃ���A�L��I�ɔ������i�ςÂ���A���͂���n��Â���A���͂���ό���ԂÂ���Ɏ��g��ŁA�ŏI�I�Ɉ����ƌւ�̎��Ă�n�������������g�݂ł���܂��B�d�v�ȃ|�C���g�́A�܂��n��̕��X������ł��B�Z���Q���ł͂Ȃ��A�n�攭�Č^�ŁA�s���Q���^�̃V�X�e���ł��B�傫�ȃL�[���[�h�͘A�g�ƍL�搫�ł��B��̂܂������łȂ��A�����ƍL��ŐF�X�ȕ��X���A�g������g�݂ł��B���̎��g�݂́A�k�C���J���ǂ���̓I�ɐi�߂Ă��Ă���A�S���ł͓��{���i�X���Ƃ����v���W�F�N�g�œ����n�߂Ă���A�k�C�����̃v���W�F�N�g�ł��B �@�ł������I�Ȃ̂́A�܂��n��̕��X�A�m�o�n��C�Ӓc�̂̕��X���A���̒n����ǂ����������Ƃ����n�攭�Ăɂ�郋�[�g�^�c�v�������ď��߂ē����o���v���W�F�N�g���Ƃ������Ƃł��B�܂�A�〈��s��������肽���Ƃ����Ă��v���W�F�N�g�͓������A�〈��s���ŁA���̒n��Ŏs�����������Ă�����X���܂Ƃ܂�A���[�g�^�c��\�҉�c�����A���[�g�^�c�v������肵����ŁA�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C�����i���c��ɒ�Ă��ď��߂ē����n�߂���̂ł��B�ꌩ�A���̎哱�̂悤�Ɍ���ꂪ���ł����A��{�I�ɂ͍��܂łƑS���t�̐i�ߕ��ŁA�s���̕��͂��Ȃ�˘f���܂��B �@�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�x���Z���^�[��������̓����ŁA�ŏ����犈���c�̂�v���W�F�N�g�S�̂��x����d�g�݂�������Ă���܂��B���x���Z���^�[�́A�k�C���S�̂̃V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�̃v�����[�V�����A�l�ވ琬�����s���܂��B���茳�́uSCENE�v�Ƃ������q�́A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���̋@�֎��ł����A����25����������Ă��܂��B����40���O�Ŕz�z���A60����S���Ŕz�z���Ă��܂����A���������L�����s���@�ւł��B �@�܂��A�n��ł́A�s���@�ւ̕��X��[�g�R�[�f�B�l�[�^���A�e���[�g�̎x���E�������s���̐�������܂��B�ł�����A�v���W�F�N�g���o���オ���Ă��闬�ꂪ�S���t�ł��邱�ƂƁA�x����V�X�e����������Ă���_���A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���̓����ł��B �@���āA�O�̘A�g�v�f�ł����A���ɂ��Ă���̂��i�ςƒn��Â���A�ό��U���ł��B�����A���ꂼ��Ɨ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�z����V�X�e���ɂ������Ǝv���Ă��܂��B�Ⴆ�Εx�ǖ����l�́A�_���i�ςŗL���ŁA��������ό��q�����܂��B�������A���̔_���i�ς�����Ă���̂́A�_�Ƃ̕���l��l�ł��B���������ƁA�ό��̃x�l�t�B�b�g���_�Ƃ̕��ɏz���܂���B�_�Ƃ̕��X�́A��p�Җ�蓙���܂߁A���_�����������āA�r�n�̃p�b�`���[�N�ɂȂ肩�˂Ȃ��ʂ�����܂��B�ł�����ό��̃x�l�t�B�b�g���_�Ƃɂ��z���A�_�Ƃ��c�߂���Ŕ_���i�ς��ێ������n�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�z������Ƃ���ɁA�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�̊��������܂��@�\���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�����悤�ɁA�m�������E��Y�ɂȂ��Ċό��q���E�����A�ό��I�ȃx�l�t�B�b�g������܂����A�����ߏ�Ȋό��q�����̒n��ɉ����A���ۑS�ɂ��̃x�l�t�B�b�g�����Ȃ��ƁA���ʂƂ��Đ��E��Y��H���ׂ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���ł́A���������n��̏z����肭����Ă��������ƍl���Ă���킯�ł��B �@���݁A�w�胋�[�g�U�A���[�g�R�ɂȂ��Ă���A�Q���c��242�c�́A���Ȃ��Ƃ�����l���Q�����Ă��܂��B�Ȃ����A�D�y�s�̓암�A�эL�s���ӁA����̍]�������Ӓn��ȂǂŁA���[�g��ڎw�����͍����铮��������܂��B���ۂ̊����Ƃ��ẮA�i�ςÂ���A�n��Â���A�ό���ԂÂ���ȂǂɊ֘A���āA�n��̕��X���l�X�Ȃ��Ƃ��s���Ă��܂��B �@�Ⴆ�A����̊����c�̂̈���s���Ă����S�~�E�����A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�̊����̒��ŁA453�������ɍL����A�A�g�ƍL�扻�̌��ʂ�����Ă���܂��B�܂��A�I�[�X�g�����A�ό��q�̓j�Z�R�ɂ������܂���ł������A�x┌⓴��ɘA��čs�����Ƃ����������͂��܂��Ă��܂��B�����ď��������ł͂Ȃ��A���͓��X�������Ă��܂��B�����������Ԃ������ĉ������Ă������Ƃ������̈�ł��B �@���܂ł́A�i�ςƒn��Â���Ɗό��ł������A�ŋ߁A������̒����lj�����܂����B�ό��ɊW���܂����A��͊O���l�ό��q�Ή��ł��B�����ւ̊ό����荞�ݐ��̓��A�����ό��q�͉������������Ă��܂����A�g�[�^�����ďオ���Ă��錴���́A�O���l�ό��q�̂������ł��B��N�Ԃɖ�50���l�����Ă���A���̂���27���l�͑�p�ł��B������9��19���ɓ��H��ʖ@�������ɂȂ�A��p�̕��ɂ����ۖƋ������s����邱�ƂɂȂ������ߊ��Ɍl���s�q��10�����A�h���C�u�ό��ɗ������Ă��܂��B�܂��A10�����{�ɏ��߂āA�}���[�V�A����h���C�u�ό��q����70�����āA��ɓ����𑖂��Ă��܂��B�V���K�|�[���Ƃ̊Ԃł͂R�N�O���炢����h���C�u�ό��v���W�F�N�g���i�߂��Ă���A���N�͂U�����炢����R���X�^���g�ɁA����10�g���炢�������Ă��Ă��܂��B�V���`���ӂŁA�O���l�ό��q�ɑ݂��o����郌���^�J�[�́A����17�N479�䂵���Ȃ������̂��A�P�N�Ԃ�1,354��ƂR�{�ɑ����Ă��܂��B���N��2,500�����Ɨ\�z����Ă��܂��B �@�����^�J�[�ʼn��ƁA�o�X�Œc�̂ŗ����肫�ߍׂ��ɉ��܂��B����ɁA50�l�̒c�̋q�ɂ͏Љ�ł��Ȃ������Ȃ������������A�n��̃��X�g�������Љ�ł��܂��B���������P��R�����炢�ŗ��܂��̂ŁA�V���K�|�[���̕��X�̏ꍇ�A���y�Y�ƐH���ゾ���Ŗ�Q���~�g���܂��B���̕��X�����10�����܂��B������ł����A�琔�S��~10���~1��2���~�Ƃ���ƁA�R���~�̋K�͂ɂȂ�킯�ł��B����ȊO�ɗ���A�h���������킯�ł�����A���Ȃ�o�ϓI���ʂ�����Ǝv���܂��B���������O���l�ό��q���A�n��̕��X�ƈꏏ�Ƀz�X�s�^���e�B����荂�����āA���s�[�^�[���ǂ�ǂ₵�����Ǝv���Ă��܂��B�O���l�ό��q�ɑ��āA�x���Z���^�[�ł͉p���ό��p���t���b�g�̔z�z�A�p�ꉹ���@�\�t���J�[�i�r�̈����A�g�ѓd�b���݂̑��o���A�ʒu���̊m�F�T�[�r�X���̎x�������Ă��܂��B �@������́A���ł��B�h���C�u�ό�������ƁA�b�n2����������r�o����̂ł͂Ȃ����B�ό��U���Ƃb�n2�̍팸�͑�������ƌ����邱�Ƃ�����܂��B��X�������������������Ƃ͎v���Ă��܂���A�G�R�c�[�����O�Ƃ��āA�Ȃ�ׂ��b�n2���o���Ȃ��^����2�N�قǂ��Ă��܂��B�����A�ǂ����Ă��o�镔���ɂ��āA���N����n�߂Ă���̂��J�[�{���I�t�Z�b�g�ŁA���s�҂̕��ɁA�o�Ă��܂����b�n2���z�����邾���̖�A�����p���A���s����ɍڂ��Ē����Ă��܂��B���N�A���ʂɍs�����c�A�[�ł́A�P�l500�~�ŁA��30�{�A���܂����B��������A�V���K�|�[�����痈���h���C�u�ό��q�ɏ��߂Ď��݁A���X�c���ʂɖ�30�{�A��A���A�I�t�Z�b�g���͗��s�҂�����炤�Ƃ������g�݂����Ă��܂��B �@������A���ʂōs���Ă��������ʂ̍ĕ҂ł��B���ʂ̓o�X��ʂ����Ȃ萊�ނ��Ă��܂������A��w�����҂Ɗw���̗A���p�Ƀo�X���T��قlj^�s���Ă��܂����B�܂��A�������ꂽ�ꏊ�ɍ����Z��X������A���̃f�B�x���b�p�[���Ŋ��̉w�����ԃo�X�𑖂点����A�s���̕a�@�����җp�Ƀo�X�������Ă���A������S�ē������܂����B����Ɍ����I�ȘH����g�ݍ��킹�A���̂Ƃ���͎�����̋��c��̂悤�ȑg�D�ł����A�V����������ʂ��^�c����g�D��ݒu���܂����B�g�[�^���ŔN��5,000���~���炢�ʼn^�c���Ă��܂����A���̂���3,000���~���́A��w��a�@�A��Ƃɏo���Ē����Ă��܂��B���̑��̕������A���������ƌ��I�ȕ⏕�ł��B�ʏ�o�X�^�s�́A�o�X���Ǝ҂ɍs���⍑���⏕�����ĉ^�s���Ă��܂������A�n��̊�Ƃ��w�ƘA�g���ĉ^�s���A���Ȃ��肭�����Ă��܂��B�ŏI�I�ɐV������Ƃ���肻�����^�s����̂��A����Ƃ����I�Ȓc�̂�����Ă����ł������W�߁A��ƂɈϑ�����̂��͌������ł����A������ɂ��Ă��A�V�����������̌�����ʂ̉^�c��̂�������Ƃ���ł���܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L��������܂����B�Ō�ɓn�ӂ���A���肢���܂��B �p�l���X�g�〈��s���@�@�n�@�Ӂ@�F�@���@���́A���Ɩ��̂���ׂ��W�A���̘A�g�����ɂǂ̂悤�Ɏ��g�ނׂ����A�Ƃ����e�[�}��^����ꂽ���Ǝv���܂��B�����T�N�O�A�s���I�ɏo�n����ہA����ɂ�����X�����𑵂��Č����Ă����̂́A�s���T�[�r�X�����Ɉ����A�E���̑ԓx���傫���A�������\���łȂ��Ƃ������Ƃł����B���������A�s�̐E�����邢�͎s�������A���Ɉ��������Ƃ������A���N����ۂɎ��Ȃ�ɍl�����̂́A�s������̂܂��Â���̐��i�ł����B���̂��߂ɂ́A���̎s���������v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA�s���̊F���s�����̐l�ԁA���邢�͍s���ƘA�g�ł���悤�Ȏd�g�݂Â������낤�ƁA�Z���������l�����N���܂����B�������A�����s���Ƃ��ď��o������10��21������Q�T�Ԃقnjo���Ă���A�e��c�̗̂v�]�E�v���łR�E�S���A�s�����Ɋʋl�߂ɂȂ�܂����B����50�`60�c�̂̕��X���A10�`15�����ɉ�ɗ��܂����A�ǂ̒c�̗̂v�]�������ł��B�����Ƃ����ƁA�⏕�������Ȃ��łق����Ƃ������Ƃł��B�N���������������m��܂��A�V�����s���ɂȂ��āA�e��c�̂̕⏕��������Ɖ\�����ꂽ�ƁA�ォ�畷���܂����B�F���⏕�������Ȃ��łق����A���܂ŎĂ���x�����k�����Ȃ��łق����ƌ����B���͎v�����̂ł����A�I���ɏo��O�A�����������悤�Șb���Ă��܂������A�s���ɂȂ��Ă݂�ƁA���̕����ԓx�������ł͂Ȃ����B�����Ȃ�A���ˑ��̑̎����܂����X�Ƒ����Ă���̂ł͂Ȃ����B �@����\���グ��ƁA�T���~���Ȃ��ł���Ƃ����c�̂�����܂����B�Ƃ��낪�A�N���1,000�~�ł��B���������̒c�̂̊������f���炵���Ǝv���Ȃ�A�����50�l���₹�����̂ł͂Ȃ��ł����B���̏�ł͐����Ɍ����܂���ł������A�S���҂ɊԐړI�Ɏw������悤�������L��������܂��B�P���Ȃ��Ƃł��������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��A���ꂪ�����銯�Ɩ��̊W�������̂��ȂƎv���܂��B �@�����Ŏ�������݂𐳂��˂Ȃ�Ȃ��ƁA�ړ��s�����A�s�����J�����s���܂����B���Ɣ�͔N�ԂQ�E�R���ł��傤���B�s�����J���ł́A�s���̕��X�ɂǂ�ǂ�s�����ɗ��Ē����A�ʂ̈Č����낤�ƁA�܂��Â���̂��ƂȂ�A���ł��悢����b���ɗ��Ȃ����ƁB���ɂ́A�����܂��A�s���������̑O�ł����̂ŁA�L��s���⍇���ɂ��Ă̍������_����̃A�h�o�C�X��A���������܂����B����ł́A�s�c�Z��Ɉڂ�̂ŁA�����̎����Ă��錢��ی����ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A�������T���Ăق����Ƃ��A19�̏��̎q�����āA�ގ��ƕʂꂽ�̂����������̂��A�����ی�������A����Șb������܂����B�s�����J���Ŏs���̐����A�����Ĉړ��s�����ł́A�e�n���c�̂ɍs���āA�F����Ɏs�s���̐������s���A���^�������܂߂Ďs���Ƌ������߂�w�͂����܂����B���̂��Ƃ́A���Ɩ��̂���ׂ��W�̌��_���Ǝv���܂��B����͏��̋��L�ł��B�������������ł����ɁA���Ɩ��̂���ׂ��p�͂��蓾�Ȃ��Ǝv���܂��B�z�[���y�[�W��C���^�[�l�b�g�A�L���g���܂����A���ꂾ���ł͕s���ł��B�����ɂ��Q�W�̍s���̊F����A�s���ɑ��Ēf�闝�R�͐��̐��قǎv�������炢�A�s���̐l�Ԃ͔\�͂�����܂����A���Ƃ�����Ă����悤�Ƃ��A���ɕ��@���Ȃ����T���\�͂����邱�Ƃ��A���Ɩ��̂���ׂ��W�̏�ŕK�v�s���̓w�͂��Ǝv���܂��B �@���Ɩ��̒��ԑg�D�ɂ��Ă��b������܂������A����͑�ϑf���炵�����A����̗���̒��ŕK�v���Ǝv���܂��B�������A�܂��s���̊F�����ˑ��̑̎�����E�p���A����ł��邱�Ƃ��A�ǂ�������܂��Â��肪�o���邩�s��������l���邱�ƁB��������́A�����������E���L���Ȃ���A������肽�����ƂɎs������ǂ��������͂��邩�A���݂̊W�������������Ă������Ƃ��A����̊��Ɩ��̂�����A�X�ɂ͘A�g�̌��ł͂Ȃ����ƁA�T�N�Ԃ̎s���̌o�����犴���܂����B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L���������܂����B�F����ɂ��肢���Ă����̂́A���̊��Â���Ƃ��̉^�c�ł������A���̒i�K�ł��݂��Ɋ���̂��b���ł���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A���c����̂��b���āA���삳����Ƃ�����ۂ������Ȃ�����A�Ō�̕����ŁA�w������Ƃ܂��Â���A���̊Ԃ̊W�́u�Ȃ����Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł����B�Ⴆ���̕ӂ�Ɋւ��āA���c����́u�N�Ɨ́v�̂��b�A�̐�����S�̂ւƂ��������b����A�w�������̋�����ǂ������Ă܂��Â���ɗ��Ƃ����ނ��A�Ƃ��������ƁB���邢�́A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�̂��b�ŁA�m�o�n�ł͂Ȃ����Ԗ@�l�̈����������ɖ��͓I���A�����������������Ƃ���ł��B�܂��A�s���̎x���̑O�ɁA������������A�s�����撣��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�ʂ�����܂��B������Ⴊ����ƁA�L�����Ă����A����S�̂ցA�Ƃ����b��������܂���B�n�ӂ���́A�̂̌��ł͂Ȃ��Ƃ�������ۂ������܂����B�s���}���̔\�͂�ς��悤�A������ŕ����̂ł͂Ȃ��A���̃j�[�Y�����ݎ��A�{��ɏ�����\�͂����˂Ȃ�Ȃ��A����͂��������t���Ǝv���܂��B���̕ӂ�ŁA���݂��c�_�ł���i�K�ɂ��Ă���̂ŁA���c����A���삳��̑�w�̋���Ƃ܂��Â���ɂ��āA�c�_���n�߂Ē����܂����B ���c�i�p�l���X�g�j �@������w�ƍ�����w�Ƃł́A�v���C�x�[�g�X�N�[���ƃp�u���b�N�X�N�[���Ƃ��ĐF�X�Ȗʂɂ����Ă̈Ⴂ�͂���܂�����A�����w�͎��̑�w�ɂƂ��Ē��ڂ̋�������ł͖����悤�ɂ��v���̂ł����A��w����芪�������I�����炷��ƁA��͂葼�̎�����w���l�ɋ����w����������Ɍ����Ă��Ă��܂��܂��B�����ł��̋�������Ɂu��w�̋���Ƃ܂��Â���v�Ɋւ��ĉ�������̒m�b��^���Ă����̂��Ƃ����v���������āA��������S�O���Ă���̂ł����E�E�E�E�B��قǓn�ӂ���〈��s�͑f���炵���w�ɂ���蒼���ꂽ�b���f�����A�����ŗႦ�ɒ[�Ȃ��Ƃ������Ă���悤�ɕ������邩������܂��A���̉w�ɂ��X�Ɋg�債�đ�w�̃T�e���C�g�ȂǂƂ������̂ł͂Ȃ��L�����p�X�ɂ��Ă��܂�����A�ǂ��Ȃ邾�낤�Ƒz�����Ă݂܂����B�u�J���`�F���^���I�v�\���ł��B�䂪��w�ɂƂ��ĂƂ�ł��Ȃ��G�����ꂽ�Ƃ����C�����܂��B�Ⴂ�w������ɊX�̂ǐ^�ʼn�������̍s�������Ă���Ƃ����������ŁA��w���w�����܂��Â���̎��H�I����⊈������ʂɈӎ����Ȃ��Ă��A�X���ɑ����傫�ȉ������N����̂ł͂Ȃ����Ǝv�킸�ɂ͂����܂���B��w������ʂ̎v���������ł��A�s�����s��������������Ƃ��������z�̓]���������ď��߂Ēn��̑�w�Ƃ��Ă̑��݉��l�������яオ���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��͕K���n�蒼����Ă����܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@��قǓn�ӂ���A��w�Ǝs�̊W�����b�������܂����A�〈��̃z�[���y�[�W�A�O�[�O�����ׂ�ƁA�����〈��傪�o�Ă��܂��B�s�s�Đ��̂��Ƃ��A�w�������̎�����o�Ă��܂��B��w�̒��ł͓s�s�Đ��ł̓g�b�v����Ă��邩��A���̈Ӗ��ł��o�ė���̂ł��傤���A�w�O�̘b��Ȃǂ킭�킭���܂��B������w�l������v���̂ł����A�s�̌������w���ɑݗ^���邱�Ƃ͂ł��܂���B�ł�����A�搶�����S�ƂȂ������Ԗ@�l�����A�Ɛő[�u�����܂߂Ȃ�����Ƃ��A�g�D�I�Ȃ��Ƃ��l����ƋC�������Ȃ�܂��B���́A��������������錍�ł���A�ʔ����Ƃ���ł���A�s���̒m�b�̏o���ǂ���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�s���Ƃ��āA��w�̍v���ɂ��Ă��b�����������B �n�Ӂi�p�l���X�g�j �@�R�[�f�B�l�[�^�[�Ƒ��c����͘b�������悤�ł��B�w�ɂ��w�̍Z�ɂɂł����B�����w�̊��������͉w�̒��ɍ��܂����A�܂��̒��ɂ����_����낤�Ƃ��A�F�X�l���Ă��܂��̂ŁA��قǂ��b�������܂��傤�B�����w�Ǝs�̊W�ł����A�����w�𑶑��������Ƃ����s���̉����A�����s���ɂȂ��ď��߂ĉ�ɏo�Ȃ������ɁA���앛�w������������������悤�ɁA�w�ȓ]���ɂ͎��ȊO�S�����ł����B���́A�|�p��X�|�[�c�͊〈��ɂƂ��Ĕ��ɗL�����Ƃ��B���݂̏��q����̎Љ�ۂ�A���U�w�K���l����A����҂̂��ꂩ��̌��N�{��͒P�Ɍ��N�����łȂ��A�����b��Â��肾�ƍl���Ă��܂��B�����b��ɂ͎�X����܂����A�|�p��X�|�[�c�̕��삪���Ȃ�E�G�C�g���߂�B��w�ƈꏏ�ɁA�s���̊F�������b��̑n�o�Ɏg�����ʂ�����A��ϗL�����Ƃ��Ǝv���܂��B�������A��w�̖{���ł���w���̕��ۑ�ɁA�ǂ�ǂ�s�����g���Ē�����A�݂��ɗǂ��W��ۂĂ�Ǝv���Ă��܂��B�L�����p�X�̘b�́A�O�����Ɍ��������Ē����܂��B ����i�p�l���X�g�j �@�w�ɂ̒��ɃL�����p�X��Z�ɂ��Ƃ́A�������Ăт����肵�܂����B����͂Ђ���Ƃ���Ђ���Ƃ���ȂƁA�����������������ĎQ��܂����B�〈��s�ɂ͑�ς����b�ɂȂ��Ă���A�F�X�Ȏ{�݂���Ē����Ă��܂��B�w�������R�Ɋ����ł��鋒�_�Ƃ��Ă��A�������Ē����Ă���r���Ȃ̂ŁA����Ƃ������͒��������Ǝv���Ă��܂��B �@��N���炱�������������n�߁A�܂��ڕW��ŏI�����n�_�͂���܂���B���N�������ł����A�����Ȋw�Ȃ̌���f�o�Ƃ������̂ɐ\�����Ă���A�ʐڂ܂ōs�����̂ł����A�c�O�Ȃ����̓I�ȋ���̂�����������Â炢�Ƃ����w�E���A���N�͒ʂ�܂���ł����B���̓_�����P���A���N�ēx�\���������A�������l�����悤�Ǝv���Ă��܂��B�����l���̌��ł́A��قǒ��Ԗ@�l�̂��b������܂������A������A��w�̒��Ɋw���̒n��A�g�������x������悤�ȁA�m�o�n�@�l����낤�Ƃ����l���������Ă��܂��B�|�p�̊w�����܂��̒��Ŋ���ł���A�X�|�[�c�̊w�����A�Ⴆ����҂�q���������w�ɌĂэ��݁A�ꏏ�Ɋ�������B�Ђ��ẮA�w���̎w���͂�A��w�̎����Ƃ��Ă̊w���̗͗ʂ��A���������d�g�݂̒��ō��߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��B���̃x�[�X�ɂȂ�̂��A��w�̊O���ɂ���〈��s�Ƃ����L�����p�X���w���ɊJ�����A���̏�Ŋw��ł��炨���Ƃ����˂炢�������Ă��܂��B�������ꂪ�A��قǗ��\���グ�Ă���܂��Â���ɂǂ̂悤�Ɍ��т����A����l�X�ȕ��Ƙb�������Ȃ���A�w������Ɠ����ɁA�܂��Â���ɍv���ł���������������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@��w�������������Ƃ���낤�Ƃ���ƁA��w�g�b�v��������܂��B�Ⴆ�ΐ쉺��̘b�ȂǁA���̂���������ǂ�����Ƃ��A�ӔC�̏��݂Ƃ��A�ޗ���̖��ȂǂɌ����邳���B���̕ӂ�̋�J�b�����������̂ł����A���̃e�[�}�́A��������ꂽ���ł���܂��B�uSCENE�v��20�������s�ŁA���O��40���z�z���Ă��邻���ł��B�������ǂ̂悤�ɂo�q���邩�A�m�E�n�E��������������������B���A���삳�A�m�o�n�����������Ƙb����܂������A���Ԗ@�l�Ƃ����ʒu�Â��ƁA�܂��Â���ɂ�������̔��M�ɂ��Ă��肢���܂��B ���i�p�l���X�g�j �@���Ԗ@�l�ɂ��Ăł����A���X�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���̘b��i�߂钆�ŁA�x���g�D����낤�Ƃ����l��������܂����B�x���̎d���́A�e���[�g�ƑS�̂ƂŐ��������Ă��܂��B�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�x���Z���^�[�͑S�̂��x�����A�O���l�ό��q���܂߃V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���S�̂̃v�����[�V�����������܂��B�g�D�`�ԂƂ��Ē��Ԗ@�l��I���R�́A�܂��ݗ����ȒP������ł��B���Ԗ@�l�͏Ȓ��̔F������܂���B������ЂƓ��l�ɓo�L����A�ɒ[�Șb�A1�T�Ԃō��܂��B�m�o�n�@�l�ƈقȂ�_�́A�m�o�n�@�l�͈��̉���[�߂��l�́A�K������Ƃ��ē���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ԗ@�l�́A���ނ��Ƃ��ł��܂��B��X�͊�ƓI�ȉ^�c���l���Ă����̂ŁA�F�X�Ȑl�̈ӌ������Ƃ͕K�v�ł����A�t�b�g���[�N�̗ǂ��^�c�`�ԂƂ��Ē��Ԗ@�l��I�肵�܂����B�������v�@�l�ł�����A�ׂ����Ă����z�͂ł����A�ׂ��������́A�ݗ��ړI�ɉ��������v�I�Ȏ��ƂɎg���܂��B �@�L��ɂ��ẮA���قǓ���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�V���A�s�u���ɑ��ă��f�B�A�����[�X���ꐶ�����A���X�s���Ă����܂��B���������܂ŁA��؏o��Ȃ��ɁA�l�X�Ȕԑg�Ɏ��グ���Ă���܂��̂ŁA����ȃ��f�B�A�����[�X�������d�v�ł���Ǝv���܂��B �@�ŋ߁A�����w�����Ƃ��܂ߐF�X�ȕ��X�Ɛڂ��钆�Ŋ����邱�ƂƂ��āA���ȓI�ȍs��������l���ƂĂ������Ȃ��Ă��邱�Ƃł��B�����Ɨ����I�Ȑl������������悤�Ȋ��������Ă����Ȃ��ƁA������܂��Â���g�D�𗧂��グ�Ă��A�Ȃ��Ȃ���肭�����Ȃ����낤�Ɗ����Ă��܂��B�ł́A�ǂ�����ė����I�ȍs��������l�𑝂₷���ƌ����A��͊w�Z����A�Љ����܂߂�����A�����Đ����I�ȗU�����Ǝv���܂��B�����ł͎����̗̂͂����ɑ傫���B �@�w�����Ƃ̐l�ɂ��Ă��A���I�Ȏd���ɉ����ہA���������͊y��������Ƃ������R�ŎQ������̂͂����̂ł����A�y���݂��珸���āA���I�Ȗ�����S���[�����Ƃ����������ɐi�ގd�g�݂��K�v�ł���Ƌ����v���܂��B�����ɒB�������i�͂Ȃ��̂ŁA�F�X�ȕ����A���̏�ɍ��킹�ēw�͂��邵���Ȃ��Ǝv���܂����A���u�����ȑO�̖�肪���Ȃ肠��Ɗ����Ă��܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@����͂R�Ԗڂ̋c�_�Ƃ��܂��傤�B�e�l�͂܂Ȃ����m�o�n�ł��ˁB��������肭�g���Ȃ���A���M����B�v���X�A�w�������̏����W�͂┭�M�͔͂����I�Ȃ��̂�����܂�����A�〈��͊��������Ă���悤�ł����B ���c�i�p�l���X�g�j �@��قǂ͎��Ԃ�����܂���ł����̂ŁA��肫��Ȃ����������ɂ��ď������߂����������ĉ������B�����b���Ă��܂���New�o�o�o�Ƃq�e�o�Ɠc���搶�̍��ꂽ�����Ƃ̊W���A�����ŏ������������Ă��������B �@�c���搶�̎�����Social Capital�E��Ƃ̐M���i�b�r�q�j�E�s���̌��͂Ƃ������L �[���[�h������܂����ANew�o�o�o�Ƃq�e�o�̍l�����̍���ɂ͂��̂R�̃L�[���[�h���[���ւ��������Ă���̂��Ǝv���Ă��܂��B�������l�I�ɂ́u�s���̌��́v�̈Ӗ�����Ƃ���͐��m�ɂ́u�s���̈ӎu�������͌ւ�v�Ɖ��߂��ׂ����Ǝv���Ă��܂��BSocial Cap-ital�Ƃ́A�k�C�^���A�ɂ�����Ƒ��I�Y�Ƃ̕��͂���萫�����ꂽ�T�O�ł���A��Ύs���͂ƂȂ�܂����A������ԍD���ȓ��{����߂́A�u�s����n��Љ���݂��l�ƌ�����W�v�Ƃ������̂ł��B��Ƃ̐M���E�b�r�q�iCorporate Social Responsibility�j�́A�v����Ɋ�Ƃ��Љ�ɖׂ������Ă��炤����ɂǂ������v�������Ȃ���Ȃ炢���A���邢�͍��s���Ă����Ɗ����͎Љ�ɂƂ��Ăǂꂾ���Ӗ����������邩��₦�Ƃ������Ƃł��B�܂��s���̈ӎu�E�ւ�́A�ŋ߂̕����Ƃ��āu�����o������͖̂��Ɉς˂�v�Ƃ���Ă��܂����A���������ĕ������Ă͂����Ȃ����̂�����͂��ł��B�q�e�o�̊�{���O�́A�������ׂ����Ƃ���������咣������ŁA���ӂ��ő�������o�����Ƃ�_���Ƃ��Ă���_�ɂ���܂��B�q�e�o�͐��i�������قǁA��{�I�Ɂu���݂��l�v�Ƃ����K�͂��A�s����s���̑�َ҂���s���Ɗ�ƂɂȂ���Ί댯�ɂ܂�Ȃ����x�Ɖ����Ă����̂�������܂���B�K�͂���O��ł���Ƃ����_���Ċm�F�����Ă��������B���̋K�͂Â����O���ɂ����āA������M�̂�������l���Ă����Ă������������Ǝv���܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�K�́A�[����S�Ċ܂߂āA�����ǂ̂悤�ɍ���Ă������Ƃ����d�v�Ȃ��b�ł����B���ɍ��삳��A���肢���܂��B ����i�p�l���X�g�j �@������̗��ȓI�ȍs���A���c����́u���݂��l�v�Ƃ����K�͓I�Ȋϓ_�ł����A��w�͊w�����g���ĐF�X���݂Ă��܂��̂ŁA���̓_�����ɏd�v�ł���Ǝv���܂��B�܂���́A��w�̒P�ʂ�^������ƂƂ��āA�n��Ŋ��������邱�Ƃ��l���Ă��܂��B���̗��ɂ͕]���������o�Ă��܂��̂ŁA���̕]���ɔ����Ċ������e����܂��Ă��܂��B������ꂽ�K�͂́A���Ƃ̓��e��]���ɉ�����Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�����ł��邩�Ǝv���܂��B�����A�Ⴆ�m�o�n�𗧂��グ�A�w�������̎��R�Ȕ��z�Ŋ�������ꍇ�ɂ́A��͂�K�͓I�Ȃ��̂�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B���̂��߂ɍs���̂��A���v�Nj��Ȃ̂��A�����̐�含�����߂邽�߂Ȃ̂��A��������Ƃ˂炢���߂邽�߂̎w�����K�v���Ɗ����Ă��܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�����w�����g���ƁA�O���̐l���u�搶�A�^�_�̘J���͂������Ă����ł��ˁv�ƌ����܂��B�J�`���Ƃ��܂��B������̗��ȓI�E�����I�̘b���܂߁A�F����ɒZ���������Ē����܂��B �n�Ӂi�p�l���X�g�j �@�F�X���b�����Ē����A��ϕ��ɂȂ�܂����B����̍s���ɑ����𗧂Ă����Ǝv���܂��B����̕����Ő\���グ��ƁA���U�w�K�̖ʂ���q���̋���A��l�̋���A����҂̋���ƁA�N��ɂ���ėl�X���Ǝv���܂����A���̌��_�͑S�ē����ŁA�����̂��Ƃ������̂��ƁA���l�̂��Ƃ��v������悤�ȋ�����s�����Ƃ��A�ŏI�I�Ȃ܂��Â���A�l����搉̂ɂȂ���Ǝv���Ă���܂��B���̒��ɂ͂�������Ƌ��������ł��傤�B���撣���āA�{���̈Ӗ��ŋ���̂܂��������������Ǝv���܂��B ���i�p�l���X�g�j �@��قnj����Y�ꂽ�̂ł����A���f�B�A�ɓ����������Ȃ�A�s������o�������A�s���̊����c�̂���o���������A���|�I�ɍ̗p�����悤�ȋC�����܂��B����͕s�v�c�ł����B �@���ꂩ��̍���Љ�E���q���Љ�ł́A�𗬐l�����ƂĂ��d�v���Ǝv���܂��B�𗬐l���ɂ́A�n���E�����̂Ȃ��l�������Ă��܂��B����Ӗ��A�V�����M���̃V�X�e����n��ɍ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���܂��B���@�́A�ꏏ�ɓ�����������܂���B�ŋߗǂ��Ǝv���Ă���̂��A�V�[�j�b�N�o�C�E�F�C�k�C���̊����Ŋ�Ƃɋ��͂����肢����̂ɁA�s���E���A�����c�̏Z�������A�ꏏ�Ɋ�Ƃ��܂�邱�Ƃł��B���ƌ����Ă��s���E�����d�b�����܂��ƁA��Ƃ͂�����������Ă���܂��̂ŁA���낢�낪�Ղ����₷���Ȃ�܂��B��Ƃ̋��͂��Ȃ���������܂��B�ł��A��肭�����Ȃ��Ă��ꏏ�ɓ������Ƃ���M���W�������Ǝv���܂��B �@�܂��A�����c�̂̒��ɁA�����̐E�����l�Ƃ��ĉ�����Ă���O���[�v������܂��B�����͌��\��肭�����܂��B���̂悤�Ȏd�����z���Ċ������Ă���s���E���ɁA���������i���d�v���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�X�s�́A�v���W�F�N�g���ƂɎQ���������E���Ɏ�����������ă`�[��������Ă��܂��B�܂��A�a�̎R���ł́A���݉ۂ̐E�����ό��v���W�F�N�g�̐E�������˂邱�Ƃ��ł��܂��B�������������Ƃ�g�D�I�ɍs���Ă����ƁA�ʔ����v���W�F�N�g����������Ǝv���܂��B ����i�p�l���X�g�j �@�h�[BOX�̐��������܂��B����́A�〈��̂h������āA�〈��̒n��}�l�W�����g�Z���^�[���w�̒��ɍ�肽���Ǝv���Ă��܂����B�����ȃT�[�r�X�X�e�[�V�������w�ɂɍ��A�T�e���C�g�Ƃ��ċ@�\���������Ǝv���Ă��܂��B�w���̊������A�h�[BOX��ʂ��Ēn��̊F����ɒ������B�����w���Ȃ������܂ł�邩�A�Ƃ������ӌ������邩�Ǝv���܂����A�����Ƃ����ǂ��A�T�L�����p�X���ێ����Ă������߂ɂ́A���ꂼ��̓������o�����Ƃ���O��ł��B��X������Ƃ���͂��邾���A�ǂ�ǂ���g�����Ƃ����C�����������Đi�߂Ă��܂��B�������w�E�����������ɂ��Ă��A���ꂩ�炶������l���Đi�߂����Ē�����Ǝv���Ă��܂��B ���c�i�p�l���X�g�j �@�����̒n���s�s�͐l��������A�Y�Ƃ̐����͎͂�܂��Ă��܂��B����u�܂��Â���v�ł͂Ȃ��A�ނ���u�܂������݁v�̎���ɓ������Ǝv���ׂ��ł��B�u�܂������݁v�̎�����}���A�〈��ɂ͑傫�ȃo�b�N�{�[��������̂��Ǝ������Ă��܂��B���x���Љ����m�M���Ƃ����m�ł���n����Z�����邱�ƂƁA���g�j�V�r�h�ȕ��ł��邱�ƁA����������ƂĂ��Ȃ����[�_�[�V�b�v���������g�b�v�����邱�ƁA���̋ƊE�l�������ɕ�����Ă��邱�ƁB�����̎����͕�����Ȃ��A�n��Đ��̑傫�ȉ\���E���ݗ͂������Ă��邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�w�ɂ̑�w�L�����p�X�����q�e�o�Ńg���C���Č�����ǂ��ł��傤���B�Ō���Y��ȁu�܂������݁v�Ɍ������āA���̃V�i���I���������B�A�t�@���h�̂�����܂ł�������l���A������s���Ă������������B�����܂Łu����S�̂ցv�̉\����M���A�Ō�܂ł��鋭���ӎu�͂������Ă������������Ƌ����v���܂��B �c���i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�܂Ƃ߂ɓ���܂����A��������̗v�f���o�Ă��Ă���Ǝv���܂��B�〈��s�̎����ʂ��Ă��A�l�X�Ȏ��_�̐��������܂��B�{���A�k�C�������痈��ꂽ���X���A�n��̓������������Ă����ۂɁA�����Ƃ������Ƃ������ċc�_����̂ł͂Ȃ��A���͌o�c�҂ł���Ǝv�������B�����A�܂��Â���Ɋւ��̂͑��l�Ȃ͂��ł�����A���c��������悤�ɁA�����ȋC�����ł̓P�K�����܂��B��������l���ċN�Ƃ���B���̕ӂ�A�v���̗͂���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B���Z�����܂߁A�g�D�����Ƀl�b�g���[�N���邱�ƁA�܂��ɘA�g���邱�Ƃ̏d�v��������Ɗ����܂����B����S�̂ւƂ������b������A���̏o�����A���̋��L������ŁA���Ɩ�����ʂ���K�v�͂Ȃ��A������̂܂��Â���c�́A���̒��ɂ���������̂܂��Â���c�̂������āA�ǂ̕����֎����Ă������́A�s��������I�őI�ꂽ���[�_�[�̎d���ł���܂��B �@�ق��܂Ƃ߂ł���܂����A���Z�b�V�������I��点�Ē����܂��B�ǂ����L���������܂����B |
| �k�C���s�s����c�̖ڎ��֖߂� | |
| �O�̃y�[�W�֖߂� | ���̃y�[�W�i�� |