|
|
|
�p�l���f�B�X�J�b�V����
���Z�b�V����
�u�n�掑���̒~�ςƊ��p�ɂ�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�~���j�e�B�����͂̋�������l����v |
|
|
|
|
|
�p�l���f�B�X�J�b�V����
���Z�b�V����
�u�n�掑���̒~�ςƊ��p�ɂ�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�~���j�e�B�����͂̋�������l����v |
|
|
�R�[�f�B�l�[�^�[�k�C�w����w�@�w�������@�@���@���@���@�A�@�F�l�����l�ł��B���̑��Z�b�V�����́A�u�n�掑���̒~�ςƊ��p�ɂ��R�~���j�e�B�����͂̋�������l����v�Ƃ��������e�[�}�ɂȂ��Ă���܂��B����̃L�[���[�h������A��͒n�掑���ł���܂��B��قǂ��ł����킹�ŁA�����Ƃ͉����낤�Ƃ������Ƃ��b��ɂȂ�܂����B���̐��������搶�Ƃقړ����ŁA�s���w�ł���܂��B�悭�s�����l����ۂɁAresource�i�����j�Ƃ͉����Ƃ������Ƃ��u�`�Řb���܂��B�u�`�ł́A�����A�����A�l�ށA���A�����I�Ȏx���ȂǁA�F�X�D������Ă��b���܂����A�����́u�n�掑���v�ƌ������ꍇ�̎����́A�Ⴆ�n�[�h�Ȍ�����{�݂Ƃ��������̂����ł͂Ȃ��A�܂��ɐl�ނ�n��̐l�X�̓����́E�����͂Ƃ��������̂��A�n�掑���Ƒ����l���Ă��������Ǝv���܂��B �@��قǂ̍���搶�̍u���ŁA�R�~���j�e�B�Ƃ͉����Ƒ��Z�b�V�����ɖ₢�������Ă��܂����̂ŁA������ɏ���܂����A������̃L�[���[�h�Ƃ��Ď����͂Ƃ������t������܂��B��������ɕ�����ɂ������t���Ǝv���܂��B�����Ƃ������{��́A�����̍��ɍ��ꂽ���t�ł��B�n�������Ƃ����̂́A�������̐V�������t�ł͂���܂���B���������̍��A���t�����ꂽ���́A�n�����u���i���́j�����玡�܂�v�Ƃ����g�����ŁA���݂͒N�����̂悤�ɂ͓ǂ܂Ȃ��ł��ˁB�u���i�݂����j�玡�߂�v�ƍl���邱�Ƃ���ʓI�ł���܂��B�Ƃ͌����܂��Ă��A���玡�߂�Ƃ͂��������ǂ��������ƂȂ̂��B����搶�̂��u���ɁA�Q���A������ǂ�����̂��Ƃ�������N������܂������A����Ǝ��玡�߂邱�ƂƂ��ǂ��Ȃ��Ă����̂��B�����������Ƃ����Z�b�V�����ɉۂ���ꂽ�ۑ肩�Ǝv���܂��B �@�Ƃ͌����܂��Ă��������Ƃ��āA�����܂߂����ɓo�d���Ă���p�l���X�g�̊F�l�́A����搶�̂��b���������߂Ē����܂����B���̍u�����e�ڎĂ��b�����邱�Ƃɂ́A�Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�ł�����ŏ��́A����搶����̖���N�̋��ɒu���Ȃ�����A�F�l���s���Ă����n�抈���A����܂ł̌������e�������b�������A��X�̐ӔC���ʂ����ĎQ�肽���Ǝv���Ă���܂��B �@����ł́A���Ԗڂɕ��삳��ɁA�n��ł̎��H�����ɂ��Ă��b���Ē����܂��B��Ԗڂ͏��삳��ɁA�n��ł̗l�X�Ȏ��H�̒�����A���Ɋ����Ă������X�̖��_�E�ۑ�ɂ��Ă��b���Ē����܂��B���̌�A���c����A�n��ł̊����̎���܂�������N���A�Ō�ɕ����搶����A���_�I�ȃR�~���j�e�B�E�n��̖������b���Ē����܂��B����ł͕��삳��A��낵�����肢���܂��B �p�l���X�g�u�����E�����k�̊X�v�t�����e�B�A�̉��@�@���@��@�`�@���@�F����ɂ��́B�u�����E�����k�̊X�v�t�����e�B�A�̉��̕���`���ł��B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B �@�܂��A���̉�͂����������Ȃ̂��A�S���C���[�W���킩�Ȃ��Ǝv���܂����A�〈��̉w�k�͂��傤�ljw�̗����ŁA���ٖ{���ŕ��f����Ă��ĂȂ��Ȃ����R�ɍs�������ł��Ȃ��B���{�����������Ȃ��悤�ȉw�k�n��ł����A�〈��̍s���̕��X�ɂ��Ă݂�A���̒n��̐l����������ɉ�������Ă���Ƃ����A�����܂ŔC�Ӓc�̂ł��B�ȒP�ɐ������܂��ƁA��X�̉�̖ړI�́A�〈��̉w�k�ɏZ�ޏZ���ӎ��̊����������C���ɐ����Ă��܂��B�ꏊ�́A�n�}�ł����Ί〈��w�̐^�゠����ŁA�l�̒��������A�w�k�n�撬��A�����c����`�����Ă��܂��B���ׂ̗ɁA�ᏼ�n�撬��A�����c��܂̒�����Ő��藧���Ă��܂��B���̓�̒���A�����c��ƁA��̒������X�̊����͈͂ň�̊���Ƃ��Ă��܂��B����ƌ����̂́A����`�����Ă���l�Ԃ��A�قڋ�̒���ɏZ��ł���Ƃ������R����ł��B  �@���̉�̔����̂��������ł����A�{���ɒP���Ȃ��̂ŁA�ᏼ�n��̒��ŁA���̎q�������̊����ǂ�����������Ƃ����b����A�����ł��邱�Ƃ��Ȃ����ƁA���N�l�ł�����삳��i�t�����e�B�A�̉��j���A������ŊȒP�Ȑ�܂���n�߂��̂����������ł����B���̕��͔_�Ƃ��c��ł��܂����A�����Ӗ��ł������ς�������ŁA�����ƍL���͈͂ŐF�X����Ă������Ƃ������ŏo�ė����̂��A��قǂ̉w�k�Ƃ�������ł��B �@��~�O�̐�܂肩��F�X�ׂ������������Ă���A��N11���ɂ��悢��ݗ�������s���A�t�����e�B�A�̉�𐳎��ɃX�^�[�g���܂����B���݂̉�����͖�40���B�E�Ƃ��o���o���ŁA�N�������30�Αォ����96�̕��܂ł����܂��B�@���A���}�Ȃǂ���؊W�Ȃ��A���ʂ��Ă���̂́A�S���玩�������̏Z��ł���n������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������z����W�܂��������o�[�ł���܂��B�����A��X���l���Ă���̂́A�����̒��������ɏd�v�����Ă���A�ǂ�Ȋ���������ɂ���������x�[�X�ɍl���Ă��܂��B �@������̌���́A��������̎Q����A�S�Ă̔N�Ԏ��Ƃ̎Q��`���A�������͒��ڊW�Ȃ��Ă��A����ɕt������l�X�Ȋ��������\�d�����āA�����炢�̐���ł��A�����̐����ɒǂ���g�Ƃ��Ă͔��ɕ��S��������͎̂����ł��B�Ȃ��Ȃ��n��̊����ɎQ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ȃ�ƁA���ʂƂ��Ė��S�������Ȃ��Ȃ��Ă���B���ꂪ���̒�����̌���ł���Ǝv���܂��B���̃t�����e�B�A�̉�̒��ʼn������Ƃ��s���ɂ́A�ꉞ���܂育�Ƃ�����A�����傫�Ȏ��Ƃ̏ꍇ�͎��s�ψ�������Ƃ������z�ł��B�������邱�ƂŁA���������悤�Ȑl����������̂ł͂Ȃ��A�����̂���n��̐l�X���A���̎��X�ɑg�D�ɎQ�����Ă����ƍl���Ă��܂��B���s�ψ�������Ƃ����i���ɑ��āA����������ΐ��Ă��������A�Ȃ���X���[���Č��\�ł��Ƃ����X�^���X�ł��B���������C�y�����A��҂��n�߂Ƃ���n��ɑS�������̂Ȃ��w�ɂƂ��āA�n��R�~���j�e�B�Ɋւ��傫�Ȃ��������ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�����A��X�̊����Ƃ��ẮA�n�抈���̓�����I�Ȗ�����S���Ă���������Ǝv���Ă��܂��B �@���N�Q���A���s�ψ���𗧂��グ�A����݂���w�k��܂���J�Â��܂����B��قǂ̋�̒�����̒���ɂ����Ƃ����͂��Ē����A���s�ψ���ɉ�����Ē����A�ϋɓI�Ɋւ���Ē�����悤�ɂȂ�܂����B�ŏ��͊F����A�����̒�����ȊO�̂��ƂȂ̂ɁA�ǂ����ĊW����Ƃ����X�^���X�ŁA��������Ƃ����������L���͈͂ŋ��͂��Ē����܂łɁA��������J���܂����B���ۂɂ́A�F�ŕp�ɂɏW�܂��ċc�_����ꂪ�ł��A��Ȗ�ȋ@�B����������Đ�܂������Ă����܂��B�S���������m�E�n�E���Ȃ��Ƃ����X�^�[�g�̒��ɂ��ẮA��r�I�傫�ȋK�͂ŁA�ƂĂ��听���ł����B �@�������n��Ƃ�������̒��ŁA�����ł��ǂ��������Ƃ����ƁA�����ٓ��őł��グ�������̂ł����A���ꂳ����������I�[�h�u��������Ă���āA��X����Еt�����I���č����������ɂ́A�S�Ă̗������Z�b�e�B���O����Ă��܂����B�{���ɒn�悾�Ȃ��Ǝv���� �悤�Ȋ������A�������Ƃ����Ē����܂����B �@��X�̊����G���A�̒��S���炢�ɍ�������������A���ɂ��ꂢ�ȏꏊ������܂��B���N�T���A��̒�����ɉ��A���1,000�~�Ŗ�̂��Ԍ����Â��܂����B�����U���Ĕ��Ɋ�����ł������A��܂�̘b�萫�̂������A200�l�̒n��Z�����W�܂��Ă�������A��̃V�[�g�ɁA���܂ʼn�������Ƃ��Ȃ��l�����Ƙb���ꂪ�ł���B���Ƃ͉w�k�Ƃ܂��ƕ����`���A���ꂩ��w�k���J������Ă����܂����A�����n��Z�����m��Ȃ��Ăǂ�����Ƃ������Ƃ���A����͉�X����̂ł͂Ȃ��A�w�k�n��U�����c��Ƃ�����X�Ɠ��l�ȍl���������Ă����ƕ�����J�����肵�Ă��܂��B �@10���ɂ͏H�̍��܂���J�Â��A�������X������ɉ��A���V�ɂ��b�܂�A��150�l���W�܂�܂����B�S��10�l�ɂP���z��A�S�������m�炸�̕��ƃn�V�ł��Ȃ���A�n��̒��ԂƂ��Ęb�����ł���Ƃ��������o���Ă��Ă��܂��B �@����ΊȒP�Ȏ��Ƃł����A���ۂɂ͂�����������Ƃ��Ǝv���܂��B�n��̒��ł��܂��傤�Ɣ��z�����Ƃ��Ă��A��̒���ɘj���Ĉē����o���E�C������̂��Ƃ��A���ۂɐl�����Ȃ�������ǂ����悤�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ��l����Ɠ�̑��݂܂����A��̃A�N�e�B�u�Ȕ\�͂�����A�ǂ�ǂ����ɂȂ��Ă��܂����B��X���ŏI�I�ɖڎw���̂́A�����悤�Ȓn��ɏZ��ł��Ă��A������O���m��Ȃ��l���قƂ�ǂł��B���̂X����ɂ́A2,000���̐��т�����܂����A���[�ʼn�Έ��A����悤�ȊW�ɂȂ��Ăق������A���k����悤�Ȋԕ��ɂȂ��̂ł͂Ȃ����B�����������Ƃ��J��Ԃ��Ȃ���A����Ă���ł��B�s���s���́A�N���痊�܂ꂽ�̂ł��Ȃ��A�n��Z���̕�����A�Z�������ɂ��Ă��A����̒n��̖����ɂ��Ă��A�ϋɓI�ɍl���Ă�����悤�ȓy���������Ǝv���܂��B�G���ł�����̐������������܂����B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L��������܂����B���܂ŗ]��Ȃ��肪�Ȃ�������̒�������A���f�I�Ɍ��т��Ă������Ƃ����A���ɉ���I�ȓ������Ǝv���܂��B�����܂��ď��삳�炨�b���f���܂��B �p�l���X�g�〈��s�E���u���a���ψ����@�@���@��@�F�@���@���͐�قǁA�����搶�𒆐S�ɂ��āA�ł����킹���������܂����B�����Y��Ȃ��ł����Ȃ�A�ȒP�Ɏ��ȏЉ������Ƃ������b���������̂ŁA�ȒP�ɂ������܂��B��{�I�ɂ̓v���O�����ɂ���ʂ�ł����A���a33�N�ɓ��u�Б�w���Q�����x��ő��Ƃ��܂����B�w��͋��ŁA�V�т̕��������ɂȂ����C�����܂����A���ꂪ�e�����đ債����Ђɂ��A�E�ł����A�����ŏ����撣���Ă݂悤�Ǝv�����̂ł����A10�����ڂɕ��e���炷���A���ė����ƌ����A�ۉ��Ȃ��ɉƋƂ̈����Ђ��p�����ƂɂȂ�܂����B���̌�A�I�[�i�[��Ђł���܂��̂ŁA���͂ǂ��Ղ�ƈ���ƂɊւ���Ă���܂����B���ł����ڏ�̎В��͂��̂܂ܑ��݂��Ă���킯�ł��B �@�{�_�ɓ����āA���u���a���ψ���Ƒ�ϖ���I�Ȗ��O�����Ă��܂����A���ꂪ�ǂ������̂����f���n��̎w����܂����B�Z�������Ƃ����Ă��A���������łł��邱�Ƃ͎��������ł�낤�B�ꍇ�ɂ���ẮA���������łȂ���ł��Ȃ����Ƃ�����Ƃ����C�������������̂ŁA�����j�R�j�R���Ȃ���A�������̂��U�炴����Ԃł��B �@�������s���Ă݂�Ɠ�����̂ŁA��ϋ�J���Ă���܂��B�Z���������ȒP���Ǝv�������R�̈�ɁA���̗��j�ς��Ԉ���Ă��邩������܂��A���{�l�͗��j�I�ɔ_�k�����ł�����A�F�Ŏx���������菕�������Ȃ���A�����̒n���L���ɂ��Ă������j������Ǝv���Ă����̂ŁA�Z�����������̉�������ōl����A��������Ȃ��Ƃ������z������܂����B �@�܂��A�n���̕��͂悭�����m���Ǝv���܂����A���u�n��ɂ��ďЉ�܂��B�i�q�〈��w����쑤�ɖ�R�q�A�u�˒n�тłƂĂ��������B�n��̒��ɂ́A��w����A���Z����A���w����A�c�t������ƁA�����n��Ƃ����Ă���Ƃ���ł��B������Ɩڂɂ͐������������Ǝv���Ă���ꏊ�ł���܂��B�����Ɍ܂̒��������A�����ѐ��͖�1,100�ˁA������ɉ������Ă���͖̂�850���сA��������76���O��̂Ƃ���ł��B16�N�V�����A�Z�������̕�����V��قǍs���A���ł��o���Ă��܂���17�N2��14���A���u���a���ψ����ݗ����܂����B����ɍs������A���f���n�悾����撣���Ăق����Ƃ������b�����܂����B���f���Ƃ������t��A���{�Ƃ����Ӗ��ɂ��Ƃ��̂ŁA�撣��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƈӋC���݂����͂���܂����B �@�Z�������g�D�̑̌��I�W�]�A�o������ɂ����������ɂ��Ă��b�������Ǝv���܂��B�����͌��\������̂ł����A��i�ł����ĖړI�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���̂ŁA������ʂ��Ă̍ŏI�ړI�́A1,100���т̐l�������{���ɒ��ǂ��Ȃ邱�Ƃł��B���ꂪ�B�����ꂽ�Ȃ�A�Z�������͂���������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���悢�惂�f���n��Ƃ��ăX�^�[�g������킯�ł����A���ł��n��̐l����͊�����킷���тɁA��������ƏZ�������͂ǂ����Ⴄ�̂��A����Ă��邱�Ƃ͓������낤�Ƃ������₪��ԑ����B�����ŏ��͕ԓ��ɍ���܂����B�����悤�Ɍ�����̂ł��B�������ŋ߂ɂȂ��āA�������������������Ă����悤�ȋC�����܂��B �@������͔C�Ӓc�̂ł���A�n��ɏZ�ސl�����S�����������Ă���킯�ł͂���܂���B���u�n��͉����������ɍ����n��ł����A����ł�76���B�c���24���́A�n��Ƃ��ē��R��ׂ��T�[�r�X���A�Ȃ��Ă����킯�͂Ȃ��B�����s���ł�����A���̐l�����ɂ��n�抈���ɎQ�����Ă��炢�A�T�[�r�X�����l�ɎĂ��炨���Ƃ����̂��A�Z�����������̊�{�ł���Ǝv���܂��B����Ɠ����ɁA�s���͍��܂ő�ϗ͂�����A�s���哱�Œ���������Ă��܂����B��������������Ă���̂ł����A�N�Ԋ�����̔����A�������Ɠ������炢�⏕�����Ă���A�����̎菕�������Ē����Ă��܂��B�����A�����ɂ̓��j���[�����Ă��܂��B����Ȏ��ƂɎg���Ă��������A�I������猋�ʂ���Ă��������B�܂胁�j���[���ŁA�⏕�����Ȃ��犈�����邱�Ƃ����������B���������b�g������܂��B�F�X�Ȓ���������āA���̂��Ƃ͂悭������܂��A��������̕��ω����ꂽ���ʂ͂���Ǝv���܂��B �@�}�C�i�X�ʂƂ��āA�Ƃ�����Η\�Z�����^�̃}���l�����ɂȂ�₷���Ǝv���܂����B�ǂ����Ă��A������⏕���͑S���g��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ肪���ł����B �@���ꂩ��n��̓����������A�Ⴆ�Η��u�͗������Ƃ��A�����������Ƃ��A�w�Z�������Ƃ��A�Ƃ������������������������Ă���̂ł͂Ȃ����B ����͉�����ɉ��ʂ�����܂��B����5����ł��A��ԑ������260�ˁA���Ȃ��Ƃ����60�˂��炢�܂ł���܂����A��������ɂ͐��ѐ��ɊW�Ȃ��Œ�����܂��B��Ќo�c�Ɠ��l�ɁA�Œ��̏k���͓���B��������Ȃ̂ł����A�〈��̎����͍̂����I�ɕ��ϒl��肸���Əゾ�ƕ����Ă��܂����A�����I�Ȃ��Ƃ��l����ƁA�⏕�������̋��ꂪ����A�����⎖�Ƃ̏k�����ڑO�ɋ߂Â��Ă���C�����܂��B�����ŁA�Z�����������́A����������_��₢�A�����b�g���ǂ��������Ă��������ۑ�ł���ƍl���܂����B�܂�A�n��Â���̃R�X�g���ǂ�����ĉ����邩�A�n��ɍ��������F���銈���E���Ƃ��ǂ�����Ή\�ɂȂ邩�A�ꍇ�ɂ���Ă͎�����������ӎ��������ƍ��܂�̂ł͂Ȃ����B��������Ƃ����̂́A�⏕���ɗ��炸�A��������ݏo�����Ƃ��l������̂ł͂Ȃ����A�ƍl���܂����B����ɂ���āA�n�戤��A�шӎ��A�x�������S�������Ɉ�܂�Ă����ƍl���܂��B �@���ꂩ��̂܂��Â���ł����A������O��ɍl����ƁA��X�n��́A�\�t�g�ʂ��d�_�Ƃ����܂��Â������������Ƃ������_�ɒB���܂����B�܂�A�A�шӎ��̍��g��A�n��łȂ���ł��Ȃ��A�n�悾����ł��鎖�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A�������Ƃ́A���ߏ��t���������悭���Ă��Ȃ���A�`�����̂��̂ɂȂ肪���ł����A�{���ɐS�̂����������̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��B���邢�͖h�ЂŁA�������N�ɋN������n�k�̕���ǂނƁA�l�����~�����W���́A�n��̐l�ł��B���h���A�x�@���A�����́A�s�̕��Ƃ����̂́A�ЊQ�̋��_�ɍs�����Ƃ������B��͂�n�悪��������L�ׁA�n�悪�x�������h�ЂłȂ���Ȃ�܂���B�����Ȃ�A�n��̎d���͖��m�����Ă��܂��B�s���͉������Ȃ��Ă����Ƃ͎v���܂���B�Љ�{�̏[���A���⓹�H�A������������肷�邱�Ƃ́A�撣���Ē��������Ǝv���Ă���܂��B �@��X�̎��Ƃ̏Љ�͖ړI�ł͂Ȃ��̂ŏȗ����܂����A�R�N�ɋy�Ԋ����̌��ʁA�������v�����Љ�܂����B�Ō�ɂȂ�܂����A�����s���A�s�����ɑ傢�Ɋ��҂��Ă���̂ł����A�������̒n��͎�����������Ƃ����Z���ӎ��̉��v���A�ꐶ�����撣�肽���Ǝv���܂��B�s���́A��v���������ɕ�����Â炢�B�����A���Ԑl�ɂƂ��ĕ�����ɂ����̂ŁA����A��Ɖ�v���������s���čs���Ē����A��������̉�v��A��������ԂŁA�s���ɕ�����₷�������������A�����̍s�������������Ɍ��J���Ē��������B���̏����A�s�����s���Ƌ��L���Ȃ���A�����̂Ƃ��Ă܂��Â���𐄐i����B���̂��Ƃ��A�R�N�Ԃ�ʂ��Ď����̌��I�Ɏv�������Ƃł��B���ۓI�Ȃ��b������ł������A�F�l���ƈꏏ�ɖ���N���������Ǝv���\���グ�܂����B�L��������܂����B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�ǂ����L���������܂����B�[���̌��ɍ��Â������̂��b�̗��ɂ́A������̓I�Ȏ���̂��Ƃ������Ă̂��Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�����܂��Ĉ��c��������肢���܂��B �p�l���X�g�C���^���N�V������������\�@�@���@�c�@�r�@�q�@����ɂ��́A�C���^���N�V�����������̈��c�ł��B��قǂ̂��Љ�̒ʂ�A���͓����̒n��E�܂��Â���Ɋւ��Z�������ƁA�E����Z�������̌��C���s���Ă���܂��B���C�̃e�[�}�́A�h�Ђ�h�ƁA���S�E���S�Ȃ܂��Â���A�j�������Q��̂܂��Â���A����͋��N�̒j�������Q���{�v��̓v�����̒��ɁA�܂��Â����h�Ђ̒j�������Q��̎��_�A�����̎��_��������悤�ɂƂ����A���܂őS���Ȃ������V�����������o����܂����B���͂��̑O���猾���Ă��āA����ƍ����ǂ������Ƃ���ŁA�������v�������Ă��܂��B�܂��ŋ߂́A�Љ��̌��C��ʂ��āA�n��Â���A�܂��Â����S���l�ނ��ǂ���ĂĂ��������A���N���炢����s���Ă��܂��B�C���^���N�V�����Ƃ������̂́A�C���^�[�l�b�g�̐��E�ŃC���^���N�e�B�u�i�o�������j�Ƃ������t������܂��B�������C���^�[�l�b�g�̐��E�ł���͓����I�Ȍ��t�ł����A�n��v����蓙�ł��ꂩ���ԏd�v�ɂȂ��Ă���̂́A�C���^�[�l�b�g�̐��E�ł͂Ȃ��A����炪�����邩�����ł̃C���^���N�e�B�u���d�v�ɂȂ�Ɗ����Ă����̂ŁA���̖��O�����܂����B�ȒP�ɂ́u�Θb�v�ƌ����Ă���܂��B���C�⒲���̒��ł��A�Θb���d�����Ă��܂��B �@�����́A����搶�̍u���̒��ɐF�X�Ȍ��t�������āA����ȃ^�C�g�������Ă��܂��Ăǂ����悤�Ǝv���Ȃ��璮���܂����B�u�����I�R�~���j�e�B�̌`���Ɍ����āA�s�s�ɂ�����ߗ����̎d�g�݁v�ɂ��Ă��b�������Ǝv���܂��B �@�܂��A�R�~���j�e�B�Ƃ��n��R�~���j�e�B�Ƃ������t�́A�ŋ߂̊�{�v��A�{��̎��Ɠ��e�̒��ɕK���o�Ă��܂��B����ɕt���̂��A�Đ��Ƃ������t�ł��B�ł��A�Đ��Ȃ̂��`���Ȃ̂��A����͌���ɓ����Č��Ă���ƁA���܂ł̂��̂��Đ�����̂��A����Ƃ��A���������n��R�~���j�e�B�Ƃ����ӎ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����ʂ������܂��B�����͌`���Ƃ������t�ƁA�ꕔ�Đ��Ƃ������t���g���Ă���܂��B�����ĕ���Ƃ����u�s�s�ɂ�����v�Ƃ������t�́A�D�y�s���̂悤�ɁA�l������ւ��}���V�����������Ă��Ă���Ƃ���ŁA�n��R�~���j�e�B��ߗW���ǂ��l��������̂��A����Ɋ�Â��Ă��b���������Ǝv���܂��B �@�܂��A�n��R�~���j�e�B�Ƃ������t�́A�{��_���̒��ŐF�X�Ȏg���������Ă��܂��B����ŁA�b��������O�ɏ��������������Ǝv���܂��B�܂��A����n��ɂ����ĉc�܂�鋤�������A����͐̂���Љ�w�̒��Ŏg���Ă��錾�t�̂悤�ł��B���̎Љ�I�����Ƃ��āA�Љ�I�ގ����A���ʂ���Љ�I�ϔO�A���ʂ̊��K�A���ʂ̊���A�����Ă��ꂪ���n��Ɋ�Â��Đ����Ă���B�Ƃ��낪�A���͗ގ����⋤�ʂ����Ɍ������Ă���B����ŃR�~���j�e�B�����Ă���Ƃ��A�n��R�~���j�e�B�̂Ȃ��肪�キ�Ȃ��Ă���Ƃ������t�ŕ\������Ă���Ǝv���܂��B �@�܂��A���̒n��ɐl�X���������邱�Ƃɂ��A����������܂�A���ʂ̓������F�߂���B����͕�����₷�����t�Ŏg���Ă���܂��B���������R�~���j�e�B�Ƃ́A���{��̒��ɂȂ��������̂ł��B�n��Љ�Ƃ����������ŁA�R�~���j�e�B�����Ƃ��Ďg���n�߂܂����B�n��ɂ����ĖڕW�Ƃ����Љ�A�т��Ӗ�����A���O�I�T�O�A���̂悤�Ɏg���邱�Ƃ�����܂��B �@�ł́A�s�s�ɂ�����ߗW�͂ǂ̂悤�ɕς���Ă��Ă���ł��傤���B�F�X�ȕ����A���������C�̒��ŁA�Q���҃A���P�[�g���Ƃ����肵��������o�ė������t�����Ă݂܂��B�܂��A�v���C�o�V�[����肽���B�ߏ��̐l�ԊW�Ɉ��̋�����u�������B���A���x�ōς܂������B����̃S�~�����ɕK�v�Ȕ͈͂̕t�������ɗ��߂����B�������O�����ׂƂ͌�������ǁA�������O�����ׂ�����̂��A���Ȃ��̂��B�t�������̓}���V�����Ǘ��l�����ł����B�Â��̎��̓`���I�Ȏ�����̂����͍D�܂Ȃ��B�`���I�ȕ��S�͂ł��邾�����������B�����������Ƃ��A�s�s�ɏZ�ޏZ���̖{���̕������Ǝv���܂��B���ꂪ���ǁA�n��R�~���j�e�B�ւ̋A�����A���ʊ���A�A�ъ��������Ƃ������ƂɂȂ��ĕ\���Ă��Ă���悤�ł��B�������Ă���n��R�~���j�e�B�̌`�����l���Ă݂�ƁA�Z�����A���ӎ��ɋC�Â��A���ʊ�����܂��̌����o�����A�A�ъ������߂Ă����v���Z�X�̕������K�v�ł���Ƃ��Ďg���Ă��邱�Ƃ��A��ԕK�v�Ȃ��̂ł���Ƌ�̓I�Ɋ����Ă��܂��B �@���N��N�ԁA�D�y�s������y���n��ōs���������ƁA�n��Â���̃R���T���e�B���O�̎d�����炲�Љ�����Ǝv���܂��B�����̂܂����i�Z���^�[���ƂƂ������̂��D�y�s�ɂ���܂��B����͕����V�N�Ɏn�߂��A���L���s���̕��������ւ̎Q���ɂ��A�n�悮��݂Ō݂��Ɏx���������𐮂��A�N�������S���ĕ�点��n��Љ�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�ڕW�Ƃ��ẮA�n��Z���̓���I�Ȏx�������A�{�����e�B�A�ɂ�镟���T�[�r�X�ƁA�ƂĂ��f���炵�����e�ɂȂ��Ă���܂��B���Ƃ̍��i�͎s�����A�ǂ��i�߂邩�́A���ꂼ��̒n��ɍ��킹�āA�A��������A������A�����ψ��Ŏd�g�݂�����Ă��������Ƃ������x�ł��B�ł�����A���ꂼ��̒n��ł������Ⴂ�܂��B�܂��Â���Z���^�[�Ƃقړ�����80��̕����̂܂��Â��萄�i���Ƒ̂��ł��Ă��܂��B 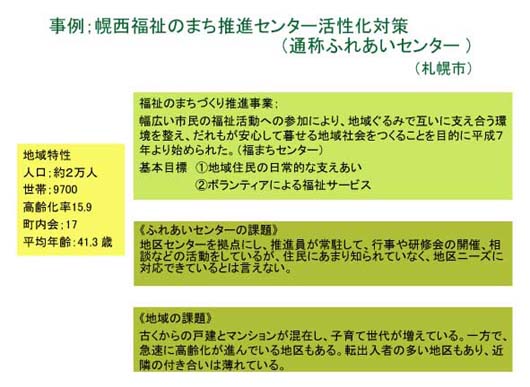 �N���b�N����Ɗg�債�܂��B �@�y���n��̒n������́A�l������Q���l�A���ѐ��͖�9,700�A�����15.9�i����17�N�j�A�����17�A���ϔN��41.3�A�Ⴂ���������܂����A�}���V�������}�Ɍ����Ă��Ă���̂ŁA�V�������オ�ǂ�ǂ����Ă��邱�ƂƁA�Â�����Z��ł�����͍�����i��ł���̂ŁA�����L���N��w�ŁA���ς����41�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����̂܂����i�Z���^�[���A�ʏ̂ӂꂠ���Z���^�[�Ƃ������O�ɕς��āA�n��Z���^�[�ɋ��_��������10�N�ȏ㊈�����Ă��܂����B���i�����풓���āA�s���⌤�C��A���k���������Ă��܂����A�Z���ɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ��A�ς���Ă����n��̏Z���j�[�Y�ɑΉ����Ă���Ƃ͂����Ȃ��ɂ���܂����B����A�ǂ̂悤�ɕ����̂܂����i�Z���^�[�����������Ă��������̂��A�P�N�Ԃ����Ď��g�݂܂����B �@�n��R�~���j�e�B�Đ��Ƃ������t���g���Ă��闝�R�́A���̐��x��g�D��������������Ƃ������ƂŁA�V�������͍̂���Ă��Ȃ�����ł��B�s�������Ƃ́A�Z���j�[�Y�����A�������ʂ��Z���Ɍ��\����B����͑S�ă��[�N�V���b�v�ŁA�ۑ�̔F���A��̌��������܂����B�����āA�Z���̈ӎ����ς����������ŁA���ʂ��ǂ̂悤�Ɋ����ɓW�J���Ă����̂��A���̗�������܂����B�Z���ɁA�Z���j�[�Y�������̂ɎQ�����Ă��炤�B����\�̐v�A�z�z���@�A���͂��钬����̑I��ȂǁA�S�ďZ���ɋ��͂��Ă��炢�Ȃ���A�Z���̎�̐����琬���邽�߁A�����̓T�|�[�g�A��̂͏Z���Ƃ����������Ői�߂܂����B�d�������_�́A���̒��ł��̒n��ɑ���A������A���ʊ�����܂��B�܂��A�ъ������@����ǂ̂悤�ɍ���Ă����̂��A������Ƃ���Ŏ��݂܂����B�ŏ��̒i�K�ł́A�����g�D�̊�������ڕW�ɁA�ӂꂠ���Z���^�[���܂����i���Ƃ̈ψ��ł���Ƃ����ӎ�������������A�����̖ړI���Y��Ă�����A��������Ă��Ȃ�����������܂��B�܂��A�A���P�[�g�ł́A�Q���ł���j�[�Y�����A���̒������ʂɑ��ďZ�����ǂ������Ă���̂��A���̈ӌ��͎��������Ƌ��ʂ��Ⴄ�̂��A��S�ă��[�N�V���b�v�Ō������܂����B�t�@�V���e�[�^�[�Ƃ��Ď������Q�����Ă��܂����A���̒i�K���ǂ�����̂��A�����C����J�Â��邩�A�ǂ�Ȑl�ɎQ�����Ă��炤���Ƃ������Ƃ́A�ӂꂠ���Z���^�[���i���̐l�����ŏ���������Ă����Ƃ������������Ƃ�܂����B �@���̌�A�u���������������ł����܂��ɂ���̂��A�ǂ����邩�v�ƁA�F����̒�����o�Ă��܂����B�u�������ʂŐF�X�Ȃ��Ƃ����������v�u��������p���Ȃ���͂Ȃ��v�u���N�x�̎��ƌv����l����ۂɁA���܂Œʂ�ɐi�߂�̂��v�u��������Ƃ��������Ă����̂��v�A�Ƃ����ӌ������R�����I�ɐ��܂ꂽ�킯�ł��B�����Ȋ����ł����A���̊����v��ɂ���荞�ނ��Ƃ��ł��܂����B���ۂɂ́A�j�[�Y�����̏����ł́A����\�A�A���P�[�g�̎���̏��ԁA���̑傫���Ȃǂ��Z���A������A���܂��̕��Ɍ��Ē����܂����B 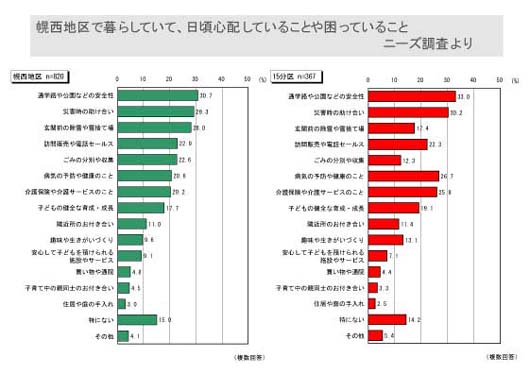 �N���b�N����Ɗg�債�܂��B �@�y���n��S�̖̂��ƁA99���}���V�����̒n���Δ䂵�Ă��b�����܂��B�S�̂Ƃ��Ă͒ʊw�H������̈��S���A�ЊQ���̏��������A����E��̂ďꂪ�g�b�v�R�ł��B�}���V�����n��ɂȂ�ƁA��͂菜��̕����������Ă��܂����A�K��̔���d�b�Z�[���X���͓����x�ɏo����Ă��܂��B�܂��A�a�C�⌒�N�A���ی����̓}���V�����̕����������炢�ł��B������A�ߏ��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��t�����������Ă��邩�A�Ƃ������������܂����B�ǂ�����قƂ�Ǖς��Ȃ��̂ł����A�������A��������x�B�قƂ�ǂ��t���������Ȃ��̂�15���ł��B���ꂪ�s�s���̋ߗׂƂ̂��t�������̎d���ł��B���ۂɂӂꂠ���Z���^�[�Ɋ��҂��邱�Ƃ́A�y���n��ƃ}���V�����n��͂قƂ�Ǖς�炸�A�ЊQ�E�a�C�Ȃǂً̋}���̃T�|�[�g�̐��A�������̒A�𗬂̏����Ƃ����̂��g�b�v�R�ł��B�Z����̏ꏊ�A�����A�ǂ������l�������ĂԂ��A�ǂ̂悤�ɐi�߂邩���A�ӂꂠ���Z���^�[���i���̐l���������������Ō��߁A�n��̓�����\���Ă��邽�߁A�I�����ċ��͂��Ă�������S������ɊҌ�����A�����Ă��炢�����Ƃ������Ƃŕ���J���܂����B 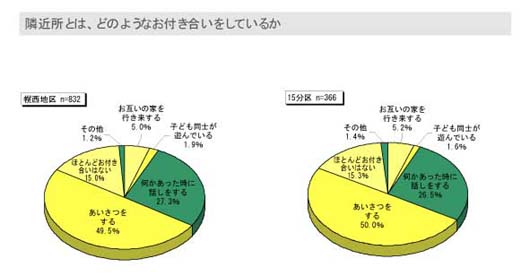 �N���b�N����Ɗg�債�܂��B �@��ł́A�������ʂɂ��Ăǂ��v�����A��b�������Ă��炢�A�}���V�����n��ƌˌ��Ēn��ŕ����čs���܂����B�ӂꂠ���Z���^�[���̂��A�m���Ă��Ȃ��Ƃ����ӌ������ɑ��������B���莖�E�S�z���ɂ��ẮA�}���V�����ƌˌ��Ăŏ����Ⴄ���ʂł����B�A���P�[�g�ɂ��Ĕ[�����Ă���Ƃ���ƁA���������������邾�낤�Ƃ�����̓I�Șb���o�܂����B�{�����e�B�A�E�n�抈���ɂ��ẮA�Q���������Ƃ����ӌ������\�������̂ŁA�F������ɋ�����A�u���̒n����̂Ă����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ����ӌ����o�܂����B �@���ʕ�����̊����ɓW�J���܂����B���̒���������I������̂��P���ł��B���N�x�̊������v�悷�鎞���Ȃ̂ŁA����ɓ�����Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�Z���^�[���m���Ă��Ȃ�����A�L������悤�B�{�����e�B�A���������l�����\�����̂ŁA���������Â�������悤�B�ЊQ�E�ً}���̕s��������Ă���l�����������̂ŁA��l��炵����҂̖h�Б����j�ɍl���悤�B��̓I�ɂ́A�L�𗧂��グ�A�{�����e�B�A���邽�߂ɁA�L��ҏW�A�q��āA�E�I�[�L���O�A�����₩�N���u�̃{�����e�B�A��W�̉��o���܂����B��l�A��l�ƃ{�����e�B�A���������Ƃ����d�b���������悤�ł��B�h�Б�Ƃ��āA�h�Е����}�b�v���쐻����B���N�x�A���̎O�̎��Ƃ������o���Ă��܂��B �@�����Ŋ������̂́A�n��Z���������̎������A���������Ō��߂邱�Ƃ��ł��钛���������Ă����B���́A���ꂪ�n��R�~���j�e�B�`���ւ̓����Ǝv���Ă���܂��B�܂��g�D�ł����A���i�ψ��������̖����E�d���𗝉����Ă��Ȃ�������A���ĐE�Ȃ̂ŕ��������̖��O�����݂��Ă���ł����B�P�N���������ŕω����Ă����̂��A�ŏ��͊F����W�܂��Ă����l�C���A�s���A�˘f���A���A�u�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Z�����̂Ɂv�Ƃ����b���قƂ�ǂł����B�j�[�Y�����̍ŏ��Ɏ�`���Ă���������Ƃ́A���͒������I�сA�ǂ����͂����߂�̂��A�������ڂ�z�z���@���ǂ����邩�A�܂��A�\�Z���Ȃ������̂ŁA2,000���S���̔z�z����e�ǂɗ��ނ��Ƃł����B���̏������班�������������ł��Ƃ����ӎ��ɂȂ��Ă��܂����B�����A�z�z�A��������_������̂ł����ōs���܂����B �@���̒������ʂ��o�������肩��A�������ς���Ă����̂́A������̍����ł��B���ʂ�20�����������̂ł����A�S�Ă̒n���30�����炢����܂����B�}���V�����n���20�������Ȃ��Ɨ\�����Ă��܂����A30���ɒB���Ĉ�ԍ��������B�F�����łƂĂ��C���悭���ꂽ�Ƃ������A�c���́A�n��ɑ���S���o�ė����B���[�N�V���b�v�̎Q���̌Ăт��������������ł���悤�ɂȂ����B�A���P�[�g���ʂ�m�邱�ƂŁA�ǂ������n�悩�����߂Č���B�܂��A�n��Ō���ƁA���ʂ̉ۑ�����邵�A�ŗL�̉ۑ������B��������ƁA�l�ōl���Ă������Ƃ��A�n��S�̂ɍL���čl���邱�Ƃ��ł��A�q�ϓI�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B�����ď��߂āA�n��j�[�Y�̋��L���F����o�ė����킯�ł��B�����Ȃ��Ă���ƁA�o�ė���ӌ��͍H�v���āA�����Ď��̍s���v��ɂȂ�܂��B12�����炢���炱�������ӎ����o�Ă��āA���ۂ̊����̎��{�ɂȂ����킯�ł��B��ԍŏ��̋��ʑ̌��⊴��̋��L�Ƃ��������́A�n��R�~���j�e�B�̌`���E�Đ��ɂ����Ĕ��ɏd�v���Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B 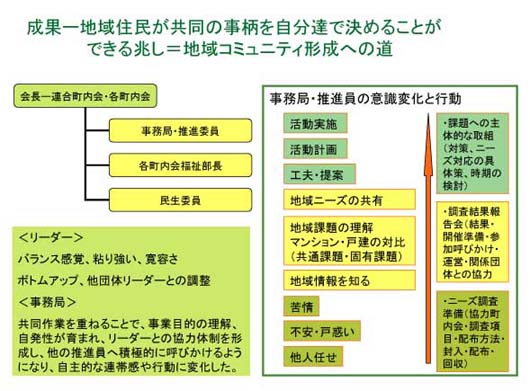 �N���b�N����Ɗg�債�܂��B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L��������܂����B�D�y�s�̂���n��ł̎���ł���܂����B����ł͍Ō�ɕ�������ɁA���������n��̂�����A�R�~���j�e�B�ɂ��āA�ŋ߂ǂ��������c�_���Ȃ���Ă���̂���������Ǝv���܂��B �p�l���X�g�D�y��w�@�w���u�t�@�@���@���@���@�q�@�F����ɂ��́B�{���͂�낵�����肢���܂��B�܂��ȒP�Ɏ��ȏЉ�����܂��ƁA���́A���͎D�y��w�ōu�t�߂Ă���܂����A���̑O�ɍ��c�@�l���{�s�s�Z���^�[�Ō����������Ă���܂����B���̍��c�@�l�́A�S���s����Ƃ����S���̎s���ō\�������g�D���e�c�̂ƂȂ�ݗ����ꂽ���̂ŁA�l�X�ȓs�s���Ɋւ��钲���E�������s���Ă��܂��B���ƃR�~���j�e�B�̊ւ��́A���̍��c�@�l�ɍݐЂ��Ă������ɁA���匤���Ƃ��Ď��g�̂��n�߂ł��B���̌����̒��ŁA�S���̎s�ɑ��ăA���P�[�g�������s������A�R�~���j�e�B����ɐ���Ɏ��g��ł���s�Ƀq�A�����O�����ɍs�����肵�A�������܂Ƃ߂܂����B����ȗ��A�l�I�ɂ����̃e�[�}��ǂ������Ă���܂��B���̌o������{���͊ȒP�ɂ������Ē��������Ǝv���܂��B �@�܂��A���Z�b�V�����̃e�[�}���u�R�~���j�e�B�����͂̋�������l����v�Ƃ������ƂŁA�ŏ��ɍl���Ă݂����̂́A�R�~���j�e�B�̋@�\�ɂǂ�Ȃ��̂����邩�Ƃ������Ƃł��B�R�~���j�e�B�̊�������ƁA�O�قǂ���Ǝv���܂��B��ڂ͎����I�Ȋ����ł��B������͐e�r�I�Ȋ����B�O�ڂ������̂���̈ϑ������ł��B�]�������Ă����̂��A�R�~���j�e�B�̎傽��S����ł��鎩����E������́A��������Ǝs�����̉������Ƃ̔ᔻ������A���̘_���������̂���ϑ����ꂽ��������������Ƃ����w�E�ł����B�������A�������{�s�s�Z���^�|�ݐЎ��ɁA�S���̎s�ɑ��ăA���P�[�g�������s�����Ƃ���A����Ƃ͏����Ⴄ���ʂ������܂����B�Ⴆ�Ύs�̍L���e�˂ɔz�z����Ƃ���������������E������Ɉϑ����Ă��鎩���̂́A3���サ������܂���ł����B���̌���A�ϑ������͂ǂ�ǂ��Ă���ƕ����Ă���܂��B����͋��炭�A������E������ւ̉��������ߔN�ቺ���Ă��邱�ƂɊW���A������E������ɓ����Ă��Ȃ����тɂ͍L��z�z���Ȃ����Ƃ����ɂȂ�A������E������ւ̈ϑ�����߂�s�������Ă��Ă�����̂Ǝv���܂��B �@�����̂��玩����E������ւ̈ϑ��ɂ��ẮA��قǏ��삳��A�����ʂƈ����ʂ�����Ƃ������b������܂������A�R�~���j�e�B�̎����͂��������Ă����Ƃ������_����́A�������������̂���̈ϑ������̌����́A�����X���ł͂Ȃ����ƌl�I�Ɏv���Ă��܂��B �@����ł̓R�~���j�e�B�̂�����̋@�\�A�����I�����Ɛe�r�I�������ǂ������W�ɂ���̂��B�����I�����Ƃ͂ǂ����琶�܂�Ă���̂��ɂ��āA���b�������Ă������Ǝv���܂��B�����ł́A�ǂ��������I�����Ƃ����̂́A�e�r�I�������琶�܂�Ă���ƌ������́A�t�Ɏ����I�������������ʁA�e�r�����܂�邱�Ƃ������悤�Ɋ����Ă���܂��B�̂̈�˒[��c�������������ƌ����Ă���܂��B��������˒[�ɏW�܂��Đ��Ԙb������Ƃ����̂́A���Ԙb�����邽�߂ɏW�܂��Ă���̂ł͂Ȃ��A�������ނƂ�����Ϗd�v�Ȏd���̂��߂ɏW�܂�A���̌��ʕp�ɂɊ�����킹�邱�Ƃ���A�F�X��b����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B���ԂƂ��ẮA�����I�����̕�����A�e�r�I���������܂�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B �@�Ƃ͂����Ă��A���͂Ȃ��Ȃ��R�~���j�e�B�Ŋ�����킹�邱�Ƃ����Ȃ��̂ŁA���삳�Ȃ���Ă��銈���̂悤�ɁA�܂��͐e�r��[�߂邱�Ƃ�����ł��傤���A�e�r�I�����������I�����ɂ��Ă������߂ɂ́A���炩�̍H�v���K�v�ł͂Ȃ����B���삳��́A�������ŐF�X����J����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B �@�����I�������ǂ̂悤�ɐ��܂�Ă��邩�A�X�ɂ��b�������Ē����܂��ƁA�m�g�j�Ɂu���ߏ��̒�́v�Ƃ����ԑg������܂��B�u�����育�ߏ��v�Ƃ������̂��o�Ă��āA��������������⒬����̕��X���������ɂȂ��Ă���悤�ł����A���ߏ��̒�͂�����B���̒�͂����������̂́A��@�ɒ��ʂ������ł���Ǝv���Ă��܂��B���X�A�����̂̕�����A�R�~���j�e�B���Đ�������ɂ͂ǂ�������������k����܂����A�R�~���j�e�B�����ɍ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���Ɋ�@������킯�ł��Ȃ��̂ɁA�s�����ǂ��ɂ��������Ǝv���Ă���߂�����܂��B��@�ł��Ȃ��̂ɁA�s�����R�~���j�e�B�Ɏ���o���K�v�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�܂��A��@�ɒ��ʂ����ۂ��A�ł��邾���R�~���j�e�B�̒�͂ɔC���A�s���͑��ʎx���ɗ��߁A������x�R�~���j�e�B�̕���˂������ƌ������A��������������肭�����ꍇ�������̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B �@������\���グ�����̂��A��قǁA����搶�̊�u���Ɂu�R�~���j�e�B�̒S����͒N���v�Ƃ�������N������܂����B�]���R�~���j�e�B�Ƃ����ƁA������E��������C���[�W�����ꍇ�����������Ǝv���܂��B����A�ŋ߂͐V�����m�o�n��{�����e�B�A���o�Ă��܂������A�����̓R�~���j�e�B�Ƃ͈Ⴄ������L���Ă���ƌ����Ă��܂����B�Ⴆ�Ύ�����E������̓����Ƃ��ẮA�n�搫�����邱�ƁA�����������邱�ƁA�n��̂قƂ�ǑS�Ă̐l���������A�n��ɂ�����l�X�ȕ�I�ȋ@�\��S�����Ƃ��������܂��B�V�ɑ��Ăm�o�n�@�l�́A���Ɋ�������n��̓R�~���j�e�B���x���Ɍ��肳��Ȃ����A�����̏Z���̕����S�ē���Ƃ����C���[�W���Ȃ��������Ǝv���܂��B�������������v���Ō��Ă��܂������A�m�o�n�@�l�̂��Ƃ�F�X���ׂĂ��邤���ɁA���̓R�~���j�e�B�̓����ł���n�搫�A�������A��I�@�\��L����m�o�n���o�Ă��Ă��邱�Ƃ�������܂����B��@�\�^�̂m�o�n��A�n��Z�����Q���^�̂m�o�n���o�Ă��Ă��邱�Ƃ��A���Љ�����Ǝv���܂��B �@�n��̕�I�ȉۑ�̉�����ڎw���m�o�n�Ƃ��ẮA�����s�̑����n��ɂ���t���[�W�������r�Ƃ����m�o�n������܂��B���̂m�o�n�́A1999�N�i����11�N�j�ɖ@�l�̔F�Ă��܂��B�芼������ƁA��ɑ����n��̏Z���ɑ��ĂƁA��������n�搫���o�Ă��܂��B��炵�S�ʂɊւ��鎖�Ƃ��s�����Ƃ�搂��Ă��܂��B�m�o�n�@�l���s�������Ƃ��āA�����A�����c��������12�Ƃ���Ă��܂������A����12�̊�������S�Ă��s�����Ƃ�搂��Ă��܂����B���������n��̕�I�ȉۑ�̉�����ڎw���m�o�n���o�Ă��Ă��܂��B �@�܂��A�n��̏Z�������ׂĉ�������m�o�n���o�Ă��Ă��܂��B�Ⴆ�Ί��̎R�����͌b�ߎs�ƍ������邱�ƂɂȂ�A�R�����Ƃ��������̘̂g�g�݂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƂɂȂ�A���R�����̋��ł܂��Â���R���Ƃ����m�o�n�@�l�𗧂��グ�܂����B �@�l���͖�5,000�l�ŁA1,500���тقǂł����A���̐��т���K���N�����m�o�n�@�l�ɉ������邩�����ł��B���̂悤�Ȃm�o�n�@�l�����܂�Ă���A�R�~���j�e�B�̒S����̑I�������L�����Ă��Ă���ƍl���Ă��܂��B���X�G���ɂȂ�܂������A������͈ȏ�̂Q�_������Ē����܂��B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�L��������܂����B�R�~���j�e�B�̋@�\�Ƃ͉����Ƃ����Ƃ��납��n�܂��āA�ŋ߂ł́A�R�~���j�e�B�Ɨގ��̊������s���m�o�n���o�ė����Ƃ������b�ł����B ���A�S�l�̃p�l���X�g�̂�������܂������A���̕��ɂ����₪����܂����炨�肢���܂��B ����i�p�l���X�g�j �@����������ꂽ�m�o�n�̊W�ł����A������̋@�\��L����@�l�Ƃ����l�����ɂȂ�܂����B�@�l�i�����������������c�̂ł���Ƃ������c�B �����i�p�l���X�g�j �@������͂m�o�n�̓����ɁA������Ƒ��݂��Ă��܂��B�����A��������܂Ƃ߂�ƌ������A�Ⴆ�܂��Â���R���́A���X���������킯�ŁA���̒��̃��x���ł܂��Â����i�߂Ă������߂̑g�D�Ƃ��č�����킯�ł��B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@������ł��ƁA�n�������@�ł́u�n���ɂ��c�́v�Ƃ����@�l�i�����Ă�悤�ɂȂ�܂������A�܂��Â���R���̂悤�ȃP�[�X�́A�����Œn�掩����Ƃ����I���������������Ǝv���܂����A�m�o�n�ɔ��肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ł����A�����鍑�̖@���x�̔���Ƃ͕ʂɍ��ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤�B �@����ł͎�����A�S�l�̊F������̂��b�ɂ��Ċ�����������܂��B�܂����삳��A��������̂��b�ł͐e�r�I��������n�߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł������A�����������Ƃ���ł͂ނ��낻���ł͂Ȃ��A��܂�Ȃǂ̊�������e�r�I�Ȋ����ɂȂ��Ă�������ۂŁA��������̃��f�����̂܂܂ł͂Ȃ����Ǝv���ĕ����Ă���܂����B�������m�F�������̂ƁA��ςȂ��w�͂Œ�����̋��͂��Ǝv���܂����A�W�܂��Ă���F������́A����搶�̂��b�ɊW���Č����܂��ƁA�Ƒ��̂���l�����͔�r�I�W�܂��Ă���̂ł͂Ȃ����B����A�S���I�ɒP�g�ҁA��l���т��������߂�悤�ɂȂ����B����������l���т̕��X�͂ǂ��������̂ł��傤���B ����i�p�l���X�g�j �@�ǂ����Ă���������𗧂��グ�邱�ƂɂȂ������Ƃ����ƁA�〈��w�ɂ��Ď����āA���N�U���ɉw�ɕ����������I�[�v�����A2009�N�ɂ͍��̊〈��s�̕����ƁA�w�k�ɂȂ��鎩�R�ʘH���ł��܂��B��ɏq�ׂ܂������A���܂Ŕ��ٖ{��������ł܂�����������Ă����C���[�W������A���R�ʘH�ݒu�ɔ����āA�w�k�̍~������ӂŋ�搮�����Ƃ��n�܂�A��C�ɗl�ς�肵�Ă����`�����X�̎��ł��B�s���哱�ŋ�抄�������ǂ�ǂ�i��ŁA���������n��Z���́A�ǂ�Ȃӂ��ɂȂ�̂��A�ǂ������C���[�W�ōL�����Ă����̂��A�S��������Ȃ��ł����B������ɂ��Ă��A�����������Z��ł���n�悪�A�ǂ�ǂ�ς���Ă����Ƃ�����C�����͊ԈႢ�Ȃ��������̂ŁA���A�A�N�V�������N�������Ƃ��v���X�ɂȂ�ƐM���ĉ�������܂����B�]���āA�e�r���ړI�̉�ł͂Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���ł��B �@�P�g�҂̕��ɂ��Ăł����A��͂�ϋɓI�Ɋւ����͂����Ȃ��B���Ԍ�����܂�ɂ��Ă��A���ꂷ��N�z�҂͐��������܂��B�Ⴂ�l�́A�q���̂��Ȃ��v�w�ŁA��X�̋ߏ��ɏZ��ł��āA�����ė�����͈ӊO�Ƃ��܂��B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@����ł͏��삳��A��ϊܒ~�̂��邨�b�ŁA�w�i�ɐF�X�Ȃ��Ƃ����邩�Ǝv���܂����B������Ɣ�ׂ����a���ɂ��Ă�����������܂������A��⌾�t��������������܂��A������}���l�������Ă����Ƃ���A���a���̓}���l�������Ȃ��̂ł��傤���B ����i�p�l���X�g�j �@��ό��������₾�Ǝv���܂��B�����ۑ�Ȃ̂������Ɏ��o���Ȃ��ƁA�}���l�����̌X��������āA�������Ƃ̈����p���ɂȂ錜�O�͏\���l�����܂��B�������͍��A����P�ʂł͂Ȃ��A�T�̒���ꏏ�ɂȂ��Ă܂��Â�������悤�Ƃ��Ă���킯�ł��B�����Ē�����łȂ��A�w�Z�A��Ƃɂ��Q�����Ă�����Ă��܂��B����ƕK�������ۑ肪�o�ė���Ƃ������҂������Ȃ���A���N�x�����Ă̊������s���Ă��܂��B�����搶�̂��w�E�̒ʂ�A�}���l�������o�ė��邱�Ƃ��\���l�����܂����A�Ƃɂ����撣�낤�A�܂��Â���̎�l���͉�X�ł���A�Z���ł���ƌł��M���Ȃ������Ă��܂��̂ŁA���̂Ƃ���͒��ʂ��Ă��܂���B�����������Ƃ͏\�����蓾��Ƃ����F���̉��A�����𑱂��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�����Ȏ��₾������������܂��A�ۑ����ɔ��@���Ă����Ƃ�����������܂����B�ۑ�͌����悤�Ǝv���A���ł�������̂ŁA���ꂪ�ǂ�ǂ����Ă����A���a�������ׂł���Ǝv���܂��B �@�����܂��Ĉ��c����A�D�y�s�̂��b�ŁA���̓����s�������猩��ƁA�K�͂��Ⴄ�Ƃ�����ۂ������邩������܂��A���̂��͐l���Q���l���x�̒n��̂��b���ł����A�����R�炵����������܂��A�������������̂��������ɂȂ����̂́A�D�y�s�����̎d�|���ł������B ���c�i�p�l���X�g�j �@�͂��B�����̂܂����i���Ƃ����ނ��A�����Ă��Ȃ��A�~�܂肩�����Ă���B����������ǂ��������̂��B���܂ŕ\�ɏo�܂���ł������A�n��̍���҂̌ǓƎ����������Ă��܂��B���̍�����ƃ}�X�R�~���ɂ��o��悤�ɂȂ�܂������A�����ψ���l�ł͕�������Ȃ�������܂����B�����鎖�ƂŁA������ɂȂ������ƁA���k���܂����B �����i�p�l���X�g�j �@����ɑΉ����邽�߂ɁA���������������o�ė����Ƃ������Ƃł��ˁB�n��̋A�����̏����Ƃ������Ƃ��o�Ă��܂������A��ʓI�Ɍ����ƁA�s�s�ɏZ��ł���l�����́A�_�R�������ɔ�ׂ�Η������X���������Ƒz���ł��܂��B���̗������X�����������ȂƂ���ŁA�����ċA�����̏������Ă��ꂽ�Ӗ��͉��ł����B ���c�i�p�l���X�g�j �@�]�Ύ҂������A�]�o���҂������Ƃ���ł��B�]�Ύ҂̎q��Đ���̍ő�̊S�����A�q���̈��S�ł��B���̒n��̏��w�Z�ł����g��ł��܂������A�ʊw�H�̈��S�A���S���Ďq�����V�ׂ���m�ۂ��Ă��������ۑ�ƂȂ��Ă��܂����B���̂��߂ɂ́A�s���̗͂Ȃǂʼn��Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�n��̐l�����������Ȃ���A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��������悤�ł��B���̒��ŁA���̒n��Ɋ����ďZ�݂����Ǝv���Ă���Ⴂ�l���������������B���̐l�����ɁA���̒n��̋���E�q��Ċ����A�����ł��ǂ��������Ƃ����v�����������̂ŁA�A�����͈�Ă���A�ڂ���������Ǝv���ă|�C���g�ɂ��܂����B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@�Ȃ�قǁB����ł͕�������A�R�~���j�e�B�Ƃ������t�͍ŋߑ����g���A����搶�̂��b�ɂ��F�X�o�Ă��܂����B�����v���ɁA�s�s���ɂ�����R�~���j�e�B�ƁA�_�R�������ɂ�����R�~���j�e�B�ł́A�����Ⴄ���̂����߂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���c����̂��b�ɂ��������悤�ɁA�s�s���̏ꍇ�͔�r�I�l�������������Ă���B����ɂ̓f�����b�g������Ǝv���܂����A�Ƃɂ����V�������������Ă��郁���b�g������܂��B�y���n��Ō����܂��ƍ����15.9���A����͐l�����������������Ȃɕς��Ȃ��킯�ł��B�Ⴂ�l���o���肷��̂ŁA10�N��ł�������͂��قǕς�炸�A�l���Z��ł���Ƃ����p�������ς��Ȃ��B����A�_�R�������ł͂Ƃɂ����l�����ŁA�D�y�̖y���n��ł͋A���ӎ��̏����Ȃǂƌ����܂������A�l�����ǂ�ǂ��āA����҂������Ȃ��悤�Ȓn��ŁA�A���ӎ������߂Ă�������̂ł��傤���B�s�s���ɂ�����R�~���j�e�B�ƁA�_�����ɂ�����R�~���j�e�B�ł́A�ǂ��������Ⴂ������̂��B�܂��A���̈Ⴂ�ɑΉ��������炩�̕�������������������B �����i�p�l���X�g�j �@��ϓ������ł��B���͎�ɓs�s���̃R�~���j�e�B�����Ă��܂������A�_�����̃R�~���j�e�B���������Ƃ�����A���̎��Ⴞ���𑨂���ƁA�s�s���ł��낤�Ɣ_�����ł��낤�ƁA�傫�ȈႢ�͂Ȃ��Ƃ������z�������܂����B�̂���A�܂���ς���̂́u�悻�ҁA��ҁA���ҁv�Ȃǂƌ����܂��B�s�s���A�_�����ǂ�����A�悻���痈���l���A���X�Z��ł���l���C�Â��Ȃ����̓y�n�̗ǂ��ɋC�Â��A�����`����������ʂ������Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�͎̂�҂Ƃ����܂������A�ŋ߂͏����̗͂��d�v���Ǝv���Ă��܂��B����͓��ɔ_�����Ɍ����邩������܂���B�_���͍��ł��j���Љ�̖ʂ�����Ǝv���܂����A���̕ǂ�ł��j�����̂��A�悻���炨�łɗ��������������Ƃ�������������Ƃ�����܂��B �����i�R�[�f�B�l�[�^�[�j �@���͂���ȂɈႢ�͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�[�����܂����B��قǂ���̎��̎���͂Ԃ����{�Ԃł��̂ŁA�S�l�̕��X�ɂ悭�����������������Ɗ��S������A���S�����肵�Ă���܂��B�t���A����������o����������������Ǝv���܂����A�c�O�Ȃ��玞�Ԃ������Ă���܂��B�c��̎�̎��ԂŁA���Z�b�V�����̂܂Ƃ߂��s�������Ǝv���܂��B �@��قǍ���搶����R�~���j�e�B�ւ̎Q���A���邢�͒n�掑�����ǂ������邩�Ƃ�������N������܂����B�����]��搶������A�u�Z���Ǝs���v�Ƃ������b������܂����B�����̃p�l���X�g�̊F�l����̂��ł́A�u�Z���v�Ƃ����l�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�u�s���v����������Ƃ������Ƃł����B�p�l���X�g�̂��b���āA�����������X���ǂ̂悤�Ɋ��p�ł��邩�A���ꂽ�������n��ɂ܂���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����]�����Ă�悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B �@�����A�����F�X�Ȏ����̂ɂ����āA�s���̕��X����������R�c�������`�����邱�Ƃ�����A��X�Ȍo�������܂��Ƃ������낢���Ƃ�������܂��B�l�X�ȋ���\�����Ă����̐l�������A���O�ҁE���\�҂Ƃ��ď��O���ׂ��ł͂���܂���B���������������Ă���l�����قǁA��U�[�����Ă����ƁA���x�͔��ɋ��������ɂȂ��Ă����Ƃ�����ʂ����x���ڂɂ��܂����B�v�͐����̖��ƌ�����ł��傤�B�s�s�ɂ͐F�X�Ȑl���Z��ł���A�F�X�ȉ��l�ς̐l���Z��ł��܂��B��l�ЂƂ肪�A�����̗��v���ő�ɂ������ƍl���Ă��邱�Ƃ��A�ŏ�����O��ɂ������������̂ł͂Ȃ����B�������邱�ƂŁA���Ȃ��̗��v���ő剻�ł���Ƃ������Ƃ��A�����ɏ�肭�����ł��邩�Ƃ����Ƃ���ɁA����搶������ꂽ�悤�ɁA�Z������s���ւ̓]���̃q���g������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@��l�ЂƂ�̉��l���ő剻���邱�Ƃ́A���̐l�̉��l�݂ɂ����āA�����̉��l���ő剻���邱�Ƃ��\�ł����A�s�s�ɂ͑����̐l�X�������ŕ�炵�Ă���Ƃ���ł�����A�������Ă���Љ�A�n��̑S�̓I�ȉ��l�����シ�邱�Ƃ��A�����̉��l�����コ���邱�ƂɂȂ�Ə�肭�`�����邩�ǂ����B�����̊〈��s�ł̎��H����̏Љ���Ă��܂��Ă��A���������ɏd�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�悭�s���̊F�l�������ɁA�u���X�͌����̖����l���Ē��������ŏ\���ł��v�Ɛ\���グ��̂ł����A��������Ȃ��Ƃ����������܂��B�Ⴆ�A�S�~���|�C�̂Ă��Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ��A�\�������I�ȉۑ�ł��B�P�l�����̕ӂɃS�~���̂Ă��������Ɩ��ł͂Ȃ����Ƃ����m��Ȃ����Ƃł��A100�l�A1,000�l���̂Ă���ǂ��������ƂɂȂ邩�B����͂܂����������̐���ۑ�ɂȂ�킯�ł��B�N���̂ĂȂ���A���H���|�����Ɋy�ɂȂ�B�����Ɍ����̖����l����ۑ肪�����āA����Ȃɓ�����Ƃł͂Ȃ��Ƃ悭���b���܂��B����Ӗ�������O�Ȃ��Ƃ��A�����ɓ�����O���Ǝv�킹�Ă��������A�R�~���j�e�B������A�����͂������Ă������߂ɔ��ɏd�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�傢�Ɋ�������������̂͑�ό��\�ł����A���Ȃ������Ɍ����Ă��A�n�掑���ɂȂ�l�X�����邱�Ƃ�F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B �@�����̃p�l���X�g�̊F����́A���̈Ӗ��Œn�掑���͂���A���͂���������Ɋ��p���邩�A���邢�͂���ɂ���Ēn��̎����́A���������Ŏ��߁A�R���g���[������Ƃ����͂����Ă��������������Ƃ��d�v�ł���Ƃ������b�������ꂼ��f�����Ƃ��ł����Ǝv���܂��B �@�������o�ł̊F�l�����A���ꂼ��̒n��ʼn����ł��邱�Ƃ������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̎��H����Ȃǂ��āA����̓E�`�̒n��ł͂ł��Ȃ��Ƃ��l���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A���̎�@�͂����ł��g���邼�A�Ƃ������_�ŎQ�l�ɂ��Ă���������ƁA�����̃p�l���f�B�X�J�b�V�����̈Ӗ����������Ƃ������ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B�F�l���ɂƂ��āA�S�l�̃p�l���X�g�̕��X�̕������ɗ��������ƂƎv���A�p�l���f�B�X�J�b�V������������Ǝv���܂��B���Ò����肪�Ƃ��������܂����B |
| �k�C���s�s����c�̖ڎ��֖߂� | |
| �O�̃y�[�W�֖߂� | ���̃y�[�W�i�� |